
-
注目の製品
 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 室内小型犬 避妊・去勢後 1歳以上 成犬用
室内小型犬 避妊・去勢後 1歳以上 成犬用
避妊・去勢後の体重管理と室内犬の健康をマルチサポート
今すぐ購入 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む -

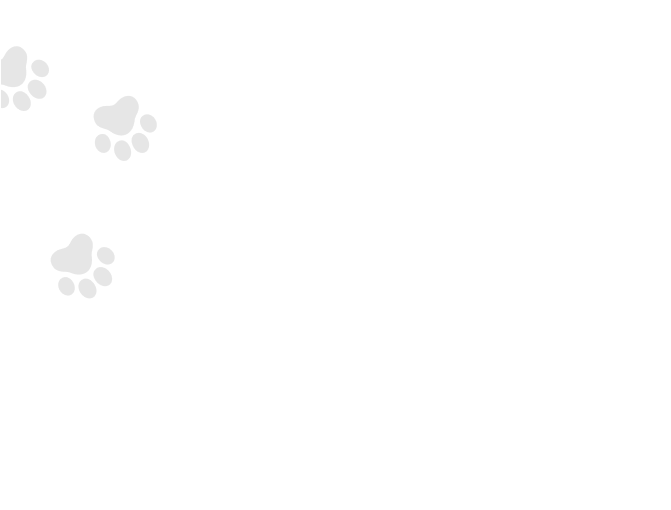
既に犬を1頭飼っている、あるいはこれから犬を迎え入れるために準備をしている方の中には、いずれは多頭飼いを検討している方もいるかもしれませんね。たしかに、犬同士が楽しそうに戯れている姿は微笑ましいものですが、複数の犬を飼う、ということにはより多くの責任や負担が伴います。多頭飼いを検討する際には、まず現在のライフスタイルや居住環境で、面倒を見きれるのかどうかよく考えてみましょう。その際には、犬種やサイズ、年齢差といったことも重要な要素になってきます。さらに、それぞれの性格や行動のニーズによる相性、将来、犬がシニアになったときのことなども想像してみてください。今回は多頭飼いについてのあれこれを紹介していきたいと思います。
犬を多頭飼いするメリット
犬が複数いるメリットは、なんとっても一緒にいられる犬同士の仲間ができることです。犬同士で仲良く過ごすことができれば、犬にとっての退屈時間が少なくなるので、家の壁や床、家具など、噛んでほしくないものへのイタズラを回避できる可能性が高まります。一緒に遊んでエネルギーを消費するので、体も心も満足すれば、飼い主への依存が少なくなります。また、犬に対する経験値が一匹でいるよりも高まるので、犬同士の社交性を身に着けやすくなる、ということもあるでしょう。もしペットがいる仲のいい友達がいるのなら、頻繁に遊びに来てもらったりして、犬同士で楽しめる時間をつくってあげるとよいでしょう。
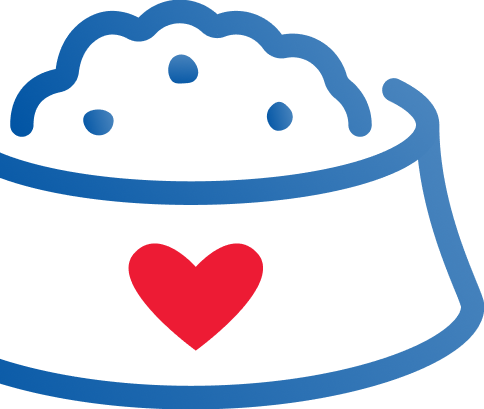

おいしいヒント
子犬は生後1年間、ワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成犬は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢犬や特別なケアが必要な犬は、より頻繁な検診が必要になる場合があります。
費用のこと
ペットを飼育するのは、当然のことながら費用がかかります。まずは犬を飼うのに身近に必要なものを考えてみましょう。首輪やリード、ドッグフードやおやつなど、それだけを見ればそこまで高価なものではないかもしれませんが、多頭になれば複数必要になりますし、犬のサイズによってはフードやおやつ等にかかる費用は結構なものになります。そのほかに、犬用のベッドやおもちゃなども必要です。仲良く共有してくれればよいですが、それぞれの好みや性格によっては、複数用意する必要があります。
ペットを飼うとなった場合に、必ず考えておかなければならないのは医療費のことでしょう。健康な状態でも、定期検診やワクチン接種、フィラリア症などの予防は犬の頭数分必要になります。さらに予定外のアクシデントで通院や入院が必要になることもあるかもしれません。そして、このような医療費以外にも、旅行や出張などで犬をホテルに預ける、あるいは世話をしてもらうためのシッターさんの費用がかかりますし、一緒に連れて行く場合でも、人間だけで行くときよりも一般的には費用がかかるでしょう。

2頭を同時に迎え入れる
犬にとっても大きな環境の変化はストレスになります。そういう点でいえば、同じ母犬から生まれた同胎犬を引き取ることは、ストレスが少なく、きょうだいでいい遊び相手にもなる、と考えるかもしれません。でも実は専門家の多くは同胎犬を受け入れることを勧めていません。というのも、同胎犬を引きとった場合、月齢によっては子犬同士の依存が強くなり過ぎて、人間へ興味を示さなくなり、人と適切な絆を結べなくなる、ということが起こる可能性があるからです。
また、現実問題として、子犬を2頭同時に世話をすることは容易ではありません。何もわからない子犬には、初日からトイレのしつけが必要があり、良くない行動にも対処しなければなりません。慣れるまではそれぞれの犬にトレーニングが必要です。それでもだんだん生活に慣れてくると、お互いのトレーニング場面を観察する余裕も出てきて互いに学習するようになり、だいぶしつけも楽になるでしょう。
保護施設で里親募集をしている犬の場合、状況によっては、仲の良い2匹を同時に引き取るような依頼があるかもしれません。もともと一緒に暮らしていた、あるいは非常に相性がよく、引き離すことで分離不安やその他の問題が起きるかもしれないと判断される場合などです。たしかに、見ず知らずの犬を同時に2匹飼うのはなかなかハードルが高いですが、犬の飼育経験があれば、このようなケースはよい選択肢の一つといえるでしょう。
時期をずらして2頭目を迎え入れる
多くのケースでは、先住犬を迎え入れてある程度犬のお世話や犬との生活に慣れてから、2頭目を飼おうか、となるかと思います。でも、その際には先住犬の性格、犬種やサイズ、行動のニーズなどをしっかり理解した上で検討してください。犬にもそれぞれ個性があることをわかってあげてくださいね。多くの場合、2頭目の犬は先住犬の行動を真似します。好ましい行動の習得が早いのは良いことですが、そうでないことも覚えますので、注意してください!
犬の相性を理解する
飼い主さんが多頭飼いを望んでいて、そのために環境を整えているとしても、実際のところ、犬がそれを望んでいるとは限りません。一般的に犬は社交性の高い動物ですが、それでも過度の怖がりだったり、神経質だったりする犬にとって、自身のテリトリーを他の犬と共有することはストレスのなにものでもありません。また、タイプが違い過ぎる犬同士もお互いにストレスになる可能性があります。犬が我を通して自分のポジションを示すような行動には、以下のようなサイン(1つまたは幾つか組み合わせて)を出します。
- つま先立ちになる、またはもう一方の犬に対して「仁王立ち」する
- 耳を前に傾けて目を合わせ、ときにマズルにシワを寄せる(ムキ顔)
- 肩の上の被毛を膨らませる(逆立たせる)
- 頭、顎または前足を他の犬の首や体の上にのせる
- 遊んでいるときに体でぶつかる、または他の犬を押したり転倒させたりする
- 他の犬のマズルや首をつかむ(かみつきに準じたような行為)
- 他の犬の上に乗るまたは押さえつける
犬が争いを避けようとする場合は、状況を落ち着かせるために「自分は怖い存在ではない」ことを伝えるサインを出します。見つめてくる犬とは違う方を向いたり、目をそらしたりするでしょう。唇をなめたり、あくびをしたり、地面を引っかいたり、ニオイを嗅いだりして、ピリピリしている犬を落ち着かせようともします。ひっくり返ってお腹を見せる行為は、緊張を和らげるための究極のジェスチャーともいえるでしょう。横になる、尻尾を振りながら地面をはう、さらにはかがむ仕草(いずれも遊びに誘っている)は、恐怖を感じていたリ優位であることを示そうと躍起になっている相手の犬の態度を変える可能性もありますが、スムーズにいかないこともあります。
多くの場合、犬は本格的なケンカに至る前に、吠えたり、そのほかのボディランゲージを使って、相手の犬に後ろに下がるよう警告します。攻撃的なサインには、睨みつける、警告的な唸り、吠え、歯をむき出した攻撃的な唸り、などの行動があります。このようなサインは、通常、その犬にとって大切な何か(おもちゃやフードなど)を守るため、あるいは距離感が近いと感じるときに出されます。もし、もう一方の犬がこのような警告のサインに対して、従うようなサインや行動をしなければ、攻撃的な犬はさらにエスカレートする可能性があります。こういった状況は非常に緊張感があり、慣れていない人にとっては怖い、と感じるかもしれません。いずれにしても事故が起こりかねない状況は避けなければなりません。
上記のような状況の場合、威嚇から突然突進したり咬みつき行動に至ったりする可能性が高いので、犬を引き離しましょう。興奮しているケースも多いので、安全のため安易に素手で犬に触れないようにします。万一咬みついてしまって両者が離れない時は、大きなタオルやブランケットを両者の上に投げたりして、気を他に向け、別々の部屋で落ち着かせます。それぞれの犬が相手の犬を許容するのにどのくらい時間がかかるのか、どこまで許容できるのか、はさまざまです。犬の性格にもよりますが、犬の引き合わせはとても慎重な作業になるので、Association of Professional Dog Trainers or the International Association of Animal Behavior Consultants*¹ のような専門機関でトレーニングや行動に関する情報を探したり、獣医師に相談して行動学の専門家やトレーナーなどを紹介してもらうとよいでしょう。

犬が仲良くなりやすい状況を選ぶ
犬を多頭飼いする場合には、少なくともあらかじめうまくいかないと思われる状況は推測して避けなければなりません。それぞれの犬の大きさや個性、年齢、性別、健康状態および活動レベルを考慮してください。一般的に考えて、高齢の犬にとって、元気いっぱいで容赦なく飛びついてくる子犬は負担になるでしょうし、大型犬で活発な性格の場合、意図せず小型犬にけがをさせてしまうかもしれません。同性同士、とくにオスの未去勢同士も縄張り意識が強く争いが起こる可能性が高くなります。複数の犬たちとより安全に暮らすため、ということでいえば、すべての犬で去勢/避妊手術をすることで、ホルモンが引き起こすさまざまなトラブルについて回避することができます。
American Kennel Club (AKC)*² によると、活動性、いわゆる運動欲求が同じような犬を選ぶととてもよい相棒になるそうです。性別が異なるペアもうまくいくことが多いです。たとえば6歳のメスのゴールデンレトリバーと4歳の活発なオスのビーグルはいいパートナーになるでしょう。また、いつもニコニコしていておおらかな犬は、大体どんな犬とでもうまくやっていけるでしょう。まとめると、後から迎い入れる犬は、社交性が高く、元からいる犬と同じようなサイズや活動性で、近い年齢を選ぶのが理想的です。
既に先住犬がいる場合、2頭目を検討する際には可能であれば直接会うような機会を設けるようにしましょう。保護施設によりますが、犬同伴で見学が可能なところもあります。あるいは、多くの施設では本格譲渡の前にトライアル期間を設けています。保護施設のスタッフと犬の性格や相性をよく相談した上で決めてくださいね。保護施設にいる犬が少し臆病な様子があっても、必ずしも2頭目としてふさわしくないとは限りません。焦らず時間をかけることによって、少しずつ心を開いてくれるようになることもあります。AKC*³ では、2頭目を受け入れる際には、その子用のケージやスペースを分けられるようなゲート、ぞれぞれの犬がある程度動き回れるようなスペースを用意して、少しずつ様子を見ながら一緒にいる時間を増やすように推奨しています。
いかがでしたか。多頭飼いには覚悟や責任はもちろん、そのための配慮や準備が必要ですが、犬たちの生き生きと楽しそうにしている様子はなにより癒されます。十分に検討したうえで、犬との生活を楽しんでくださいね。
参照先:
*1 https://apdt.com/
*2 https://www.akc.org/expert-advice/puppy-information/when-should-you-get-a-second-dog/
*3 https://www.akc.org/expert-advice/training/how-to-introduce-dogs/


エイミー・ショジャイは、認定動物行動コンサルタントであり、ペットのケアと行動に関する全米的に知られる権威です。獣医技術者としてキャリアをスタートし、35冊以上の処方箋となるノンフィクションのペット関連書籍を執筆し、受賞歴も多数あります。
関連製品

【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

本来の免疫力を保ち、子犬の健康的な発育をサポート

免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート

【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

犬に知られずにダイエットさせる
低カロリーのフードで、愛犬の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
犬に知られずにダイエットさせる
低カロリーのフードで、愛犬の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。








