
-
注目の製品
 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む -

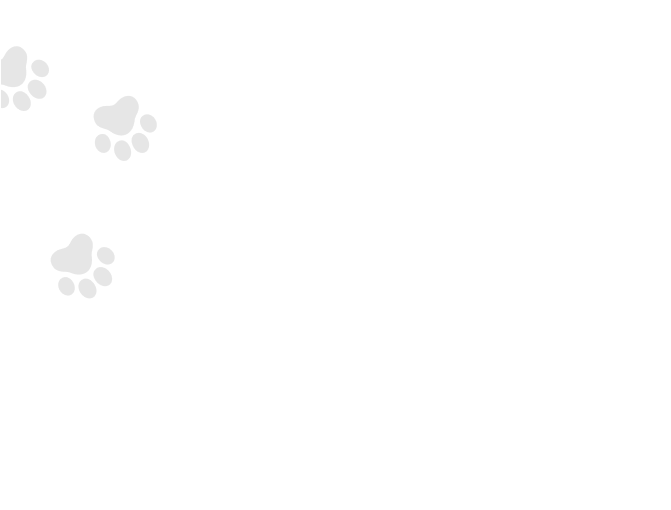
愛猫がもしかして太っている?肥満かな?と考えてみたことはありますか?人間にとっては、最近ズボンがちょっとキツくなったなと感じるなど、体重がちょっとでも増えたことに気づきやすいものです。しかし、猫の場合、肥満状態にあるかどうか気づいてあげられるのは飼い主であるあなただけです。もし、愛猫が太っている事に気が付いたら、以下のヒントをフードやケアなど肥満対策に活用してください。
猫の肥満は何キロから?
猫が肥満かどうかを判断する上で、「体重」という単一の指標で定義することはできません。一般的な猫の体重を15~20%上回っていたらという考え方もありますが、メインクーンなどの大型の猫種はもともと体重が重いですし、個体差もあるため一概にはいえません。
猫が肥満かどうかの見分け方
では、どのようにすれば猫が肥満かどうか見分けられるのでしょうか?それは、愛猫の体格とBFI(体脂肪インデックス)、BCS(ボディコンディションスコア)などを照らし合わせることで、標準なのか肥満なのかを確認することができます。
猫の肥満の兆候について
最近、猫が太ってきたけどかわいいからとほったらかしにしていませんか?もしかすると、肥満になる兆候かもしれません。肥満は様々な健康リスクをもたらすので、以下のような兆候が見られないか確認してみてください。
猫の肥満の兆候1:過剰な体重変動
それは体重の過剰な変動です。信じられないかもしれませんが、愛猫が痩せていっている状態も、注意が必要です。これは特に、愛猫の体重が過剰に増えた後、何らかの健康上の問題を抱えた場合によく起こります。体重の増加に繋がる病気もありますし、体重の増加によって身体が重くなったことにより、体調不良をひきおこし結果として痩せてしまう、ということもあるのです。もし、愛猫が何らかの健康問題を抱えているようであれば、かかりつけの動物病院に必ずご相談ください。愛猫に本当にダイエットが必要であるかどうかを判断することが出来ます。
猫の肥満の兆候2:常に空腹状態
もう一つ、猫が肥満への道を辿っている兆候として、常にお腹をすかせているという場合です。そのような場合には、繊維質を多く含むフードを与えることによって、より長い間満腹感を与えることが出来ます。また高たんぱく質、低炭水化物の栄養組成は、猫のエネルギー代謝を変化させて減量できることも知られています。必要としている栄養素をきちんとバランス良く与えることによって、愛猫はより活動的になり、健康的な理想体重の維持につながります。
猫の体型を外見や実際に触れて確認、評価するボディ・コンディション・スコアというツールがあります。肋骨を始めとする骨の見え具合をもとに5段階で体型を評価できます。具体的にはペットのボディ・コンディション・スコアとは?のページで詳しく説明しているので、合わせてご参照ください。
猫の肥満の兆候3:運動量の減少
肥満の兆候として以前に比べて活動量が減っている場合があります。去勢あるいは避妊された猫は手術前と比べて、身体の代謝のスピードが遅くなっています。活動量が減っているということは、必要なカロリーも減っているという意味です。このような場合、カロリー摂取量を調整しなければ体重は増え続け、肥満になるかも知れません。
特に注意が必要な肥満猫の兆候
猫が肥満の状態で下記の症状が見られる場合、早めに動物病院を受診してください。
- 水をよく飲む
- おしっこの量が増える
- 薄い色のおしっこが出る
- 以前よりもよく食べる
肥満になると糖尿病になる可能性が高くなります。糖尿病は尿の量が増え体内の水分が奪われるため猫の喉が渇き水をよく飲む症状が発生します。肥満、太り過ぎの愛猫の場合、これらの症状を見逃さないように注意しましょう。
なお、病状が進むと元気消失、嘔吐などがみられ、痩せて、毛艶が悪くなってきます。その状態になって気づくペットオーナーも多くいます。飲水量・尿量に変化が見られたら、早めの動物病院受診を心がけてください。
肥満による猫の寿命への影響
肥満は猫の寿命に対してネガティブな影響を与えるとされています。それは、病気のリスクが高まることに加え、肥満によって治療や管理が難しくなることがあるからです。また、運動不足になることで筋力が低下するなど、猫の寿命に影響を与える様々な変化が起こる可能性があります。
肥満が原因で起きる猫の病気
猫の肥満は病気の原因となることもあります。
体重が重くなることで関節への負担が増加し、関節炎や椎間板ヘルニアなどの関節の病気を起こしやすくなります。脂肪が増えることで、糖が細胞内に取り込まれにくくなり、糖尿病のリスクが高まります。また、肥満の猫は心臓病になりやすい傾向があったり、腹腔内脂肪や皮下脂肪の影響で呼吸機能が低下する場合もあります。
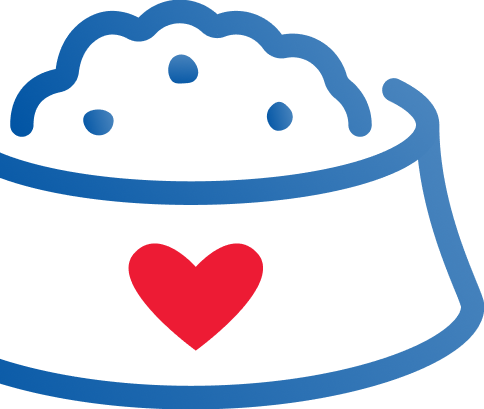

おいしいヒント
子猫は生後1年以内にワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成猫は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢猫や特別なケアが必要な猫はより頻繁な検診が必要になる場合があります。
猫の肥満の原因
猫の肥満の原因は大きく2つ、食べ過ぎと病気が原因となる肥満に分けられます。
食べ過ぎによる肥満
多くは、運動不足によるものと食べ過ぎによるものです。
避妊や去勢手術によって太りやすくなることも言われていますし、遺伝性のものや、高齢になり、代謝が落ちてきた結果太りやすくなる傾向があるといったことも言われております。高齢猫の変化を踏まえたフードについてはこちらをご覧ください。
病気による肥満
病気が原因となる肥満は、甲状腺機能低下症やクッシング症候群などの内分泌系の疾患が代表とされています。
なお、病気になった際に服用する薬の副作用による肥満もあります。
肥満の原因を正しく理解して肥満の解消を目指しましょう。なるべく早めに動物病院で獣医師さんに原因を調べてもらいましょう。
環境とペットオーナーとの関係による肥満
肥満の原因として下記の2つについても考え直してみることが必要です。
- ペットオーナーによる食べ物の選定
- 飼育スペース、環境の最適化
ペットオーナーが愛猫の最適な栄養・給与量を理解できておらずフードや過剰な栄養になり肥満につながっていることがあります。また愛猫の品種やサイズ、運動不足などで肥満に至ることがあります。
猫の肥満を予防する方法
愛猫の肥満はさまざまな病気になる可能性を高めるため、日頃から肥満予防を心がける必要があります。ここでは肥満の予防方法をご紹介します。
給与量の最適化による肥満予防
給与量が適切か、品種、年齢、現体重、日頃の運動量に合わせて最適化することが望まれます。
動物病院で獣医師に相談しましょう。
キャットフードの見直しによる肥満予防
キャットフードを繊維質を多く含むフードを与えることによって、より長い間満腹感を与えることが出来ます。また高たんぱく質、低炭水化物の栄養組成は、猫のエネルギー代謝を変化させて減量できることも知られていま
す。このようなキャットフードにすることで肥満防止を期待できます。
運動量増加による肥満予防
屋内で飼育している愛猫のためにキャットタワーを設置したり、定期的におもちゃで遊んであげることで運動量を増やし肥満を防止します。
運動量を増やすためのポイント
猫は本能的に狩りを行う動物です。この本能を活かし、遊び心のある形で、愛猫がこの本能を活かせる「かくれんぼ」、あるいは「障害コースゲーム」など、クリエイティブなゲームを創り上げるのは、愛猫にとっても飼い主さんにとっても楽しいことです。新しいおもちゃで、より活動的になれるかも知れません。
まずは、1日5分ほど、遊びの時間を作りましょう。数週間後には、体重減量のため、1日少なくとも10分は運動をさせましょう。活動量の増加は、減量に繋がり、また、継続して健康的な体重を維持出来るようにもなるかもしれません。
定期的な体重管理による肥満予防
愛猫のライフステージに合わせて定期的に体重測定を行い、猫の肥満を予防しましょう。
事前に獣医師に相談し、理想体重を把握し、肥満予防を目指します。
生後4ヶ月程度までは週に1度体重を測定し、それ以降は月に1度体重を測定し獣医師に相談した理想体重に近いか確認、記録することをお勧めします。肥満や太り気味の際には運動量を増やす、キャットフードを見直す、獣医師に相談するなどの対策を行いましょう。
肥満猫の食事について
愛猫が肥満になってしまった場合、まずフードを給与しすぎている可能性があるため、下記ヒルズの給与量ガイドプログラムで愛猫の適切な給与量を確認しましょう
適切な給与量が分かったところで、運動量を増やすなどの方法も取り入れます。栄養が足りなくなってしまわないようにキャットフードも適切なものを選択しましょう。
ヒルズのおすすめの体重管理のキャットフードをご紹介
ヒルズ プリスクリプション・ダイエット(特別療法食)〈猫用〉 メタボリックス ドライ
本来の健康的な代謝を保ち、低カロリー*1で減量に役立つことが科学的に証明された療法食です。
*1 カロリー約14%減 (当社サイエンス・ダイエット〈プロ〉 成猫 1~6歳 毎日の活力維持機能と比べて)
※必ず獣医師の指導の下に、給与してください。
健康的な体重を維持し猫の肥満予防をするためのステップ
愛猫の健康的な体重を維持することは、ペットのQOLを向上させるだけではありません:それは、飼い主にとっても、余計なお金がかからない、という事になります。ペットの飼い主は、お金をかけて、肥満が引き起こす問題と戦っています。現在肥満である、あるいは肥満傾向の場合でも、フードの量を確認することは、大切なことです。愛猫が健康な体重を維持するため、活動量を常に確認し、かかりつけの動物病院で定期的に体重や栄養指導を受けましょう。
どんなにポッチャリしている猫でも、飼い主のサポート次第でより健康的な生活を送るチャンスがあります。愛猫が肥満気味でもあきらめないで!
ダイエットをさせたい方は、参考記事「猫のダイエット方法やフードについて」もご覧ください。


クリッシー・クリンガーは教育者、ライター、そして2人の子供、3匹の犬、3匹の猫の母親です。愛犬のジェイクは、隙あらば彼女の膝の上に乗るのが大好きです!ペンシルベニア州の田舎で、アクティブで環境に優しいライフスタイルを楽しんでいます。
関連記事

猫の食性を理解して、理想的な食事回数を覚えておきましょう。また自動給餌器を利用する方法についても解説します。

ウェットフードは一般的に猫が好み、味にうるさい猫にはぴったりな選択肢になります。ウェットフードの利点や与え方について確認しておきましょう。

胃腸の弱い猫について、深掘りしていきます。このようなケースでの食事の役割について学びましょう。

トイレトレーニングをはじめ、様々なシチュエーションにあわせた愛猫のしつけにチャレンジする方も多いですよね。良い行いにはごほうびを与えるなど、トレーニングの目的にあわせた最適な方法をご紹介します。

猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。





