
-
注目の製品
 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む -

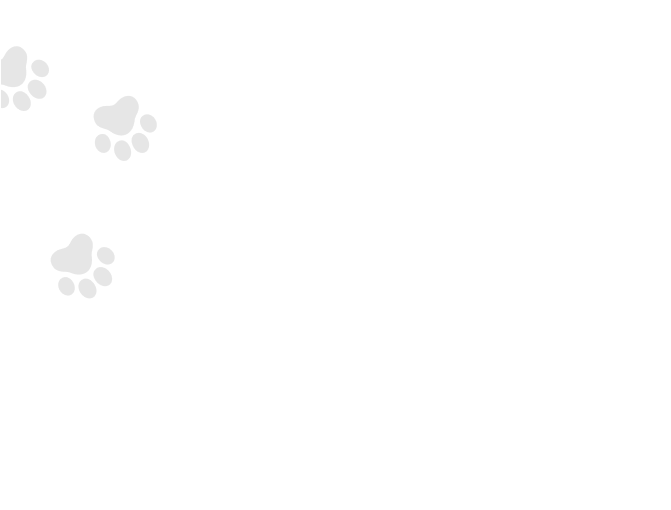
獣医療は日々発展し、ペットのための食事や医薬品などはどんどん良いものが開発され、飼い主さんのペットの健康に対する意識も高まって、この数十年でペットの寿命は大きく伸びました。それにより、シニアと呼ばれる世代の高齢のペット達も増えています。毎年欠かさず獣医師による検診を受け、ドッグランや旅行など様々なところにも一緒に連れて行き、何年にもわたって健康だったとしても、年齢を重ねていくうちに、視覚や聴覚、運動機能などが少しずつ衰えてくるのは仕方のないことです。それは人間でも同じですよね。
耳が遠くなるというと、このような年齢的な要因によることが一般的ですが、それ以外でも若くして聴覚にトラブルが起きることもあります。普段の生活の中で呼びかけに反応しにくくなったり、食事を準備している音に犬が興味を示さなくなった、といったことで気づくことが多いかもしれません。今回は、聴力の低下が犬に認められたときに、考えられる原因や対処法、お家でできる環境の整備やケアについてご紹介します。犬が障害を抱えることは、大変心苦しいことではありますが、たとえ耳が聞こえづらくなっても、愛情と適切なケアをすることによって、不便や不快を感じずに楽しく生活することができます。犬とどのようにコミュニケーションを取り、どのように安全を確保するか、犬の状態や性格を踏まえて、考えてみましょう。
犬の難聴や聴覚喪失の原因
George Strainの著書 「Deafness in Dogs and Cats」によると、先天性の原因により、生まれながらにして聞こえないか、あるいは聞こえづらいケースがあります。後天性の場合には、様々な原因によって聴覚が低下、あるいは失われることがあります。その中でも加齢は、犬の聴覚が低下するもっとも多い原因の1つです。さらに、犬の聴覚喪失や難聴の原因には、耳の外傷や炎症性疾患、異物やポリープなどがあります。また、薬剤や化学物質の毒性によって犬が聴覚を失う場合もあります。
出生時に聴覚を失っていたリ、時間の経過とともに聴覚を失ったりするケースが多い犬種がいることも知られています。 ルイジアナ州立大学獣医学部の神経科学の教授であり主任獣医学研究員であるStrain先生は、先天性の聴覚喪失がみられた犬種(出生時の聴覚喪失の発生頻度が非常に高い犬種を含む)100種類を特定し、一部の犬種は他の犬種よりも生まれながらにして聴覚がないことがはるかに多いことを明らかにしています。興味深いのは、Strain先生が、白色色素の犬種の方が聴覚喪失になりやすいかもしれないと述べていることです。そして、Lowell J. Ackermanの著書 「The Genetic Connection: A Guide to Health Problems in Purebred Dogs」でも、ダルメシアンは先天性の聴覚喪失の割合が非常に高いと記されています。
聞こえているかを確認する方法
まずご自宅で愛犬の聴覚を確認する方法をご紹介します。犬が寝ている間か、まったく別の方向を向いているときに犬の後ろに立ち、存在を犬に気づかれないようにします。犬がこちらを見たり、動きを感じたりできないようにしてください。(できるだけ音を立てないように静かに行いましょう)それから大きな音を立てます。愛犬は音に気が付きますか? 耳を立てたり振り返ったりしますか?
また、音の大きさや音域によって反応が変わるかどうかも確認してみましょう。鍋をたたいて低音域の音が聞こえるか、手を大きくたたいて中音域の音が聞こえるか、口笛を吹いて高音域の音が聞こえるかなどです。反応がない、あるいはうすい場合、耳が聞こえていないか聞こえづらい可能性があります。その場合には、動物病院を受診して耳の検査を受けましょう。
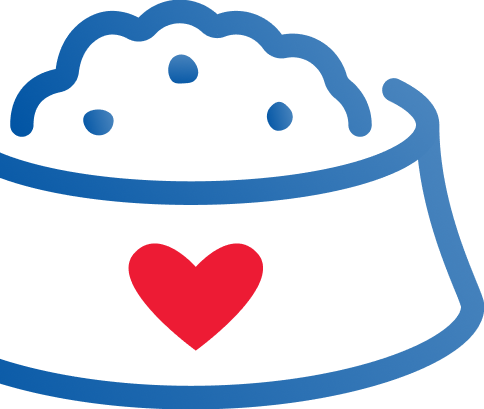

おいしいヒント
子犬は生後1年間、ワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成犬は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢犬や特別なケアが必要な犬は、より頻繁な検診が必要になる場合があります。
聴覚のトラブルが起きないようにするためには
原因によっては、あらかじめ対処することができないものもありますが、中には日頃から心がけることによって、聴覚のトラブルができるだけ起きないように対処できることもあります。まず、犬の耳を常に清潔な状態に保つことで、難聴になるリスクを下げることができます。ただし、犬の耳のケア方法については、ご自身で行う前に必ず獣医師に犬の耳の掃除方法を習うようにしてください。安全に正しくできるようになったら、ご自宅で日常的に愛犬の耳の掃除をするようにしてください。
さらに、人間と同様に、聴覚にトラブルを起こしかねない大きな音に、犬を近づけないように注意することも大切なことです。犬の耳は人間よりもずっと感度が高いため、大きな音は犬の聴覚にとって、より大きなリスクとなります。大音量で音楽を聞いたり、ご自宅でバンド演奏の練習をしたりする場合には、必ず犬は別の部屋にいてもらうようにしてください。レジャーなどで花火をする場合にも、犬を怖がらせないという意味だけではなく、大きなドーンという音を聞かせないように、室内に犬を入れておくようにしてください。
そして、これは聴覚にトラブルに関わらずですが、栄養管理はさまざまな器官の健康維持のためにもとても重要です。品質が高く、栄養バランスの取れた栄養価の高いフードを与え、常に十分に水分補給できるようにします。
コミュケーションの取り方や環境に配慮する
 犬が聞こえづらくなってきて、まず考えなければならないのは、コミュニケーションを取る新しい方法をお互いに学習することです。基本的には言葉によるトレーニングの命令に、手を使ったサインを取り入れるようにします。突然聴覚を失った場合には、犬自身が困惑してパニックになり、なかなかトレーニングが難しい場合もありますが、根気強く対応し、手を使ったトレーニングプログラムを習得できるようにより集中的に頑張りましょう。聴覚を失った場合、犬でも私たち人間と同じように、その状況に慣れるまでには時間を必要とします。あきらめず、一緒にやりとげましょう。
犬が聞こえづらくなってきて、まず考えなければならないのは、コミュニケーションを取る新しい方法をお互いに学習することです。基本的には言葉によるトレーニングの命令に、手を使ったサインを取り入れるようにします。突然聴覚を失った場合には、犬自身が困惑してパニックになり、なかなかトレーニングが難しい場合もありますが、根気強く対応し、手を使ったトレーニングプログラムを習得できるようにより集中的に頑張りましょう。聴覚を失った場合、犬でも私たち人間と同じように、その状況に慣れるまでには時間を必要とします。あきらめず、一緒にやりとげましょう。
そして、このようなハンドサインのほかにも、犬が日常生活のいろいろなことを理解しやすいように、聴覚以外で認識できる指標を工夫するのもよいことです。たとえば、夕方になって庭から家の中に戻る時間になったら、懐中電灯を点灯させて、犬にそれを知らせたり、就寝時間であることを知らせるために、部屋の証明のオンオフを1回繰り返したり(消して⇒つけて⇒消す)するなどです。また、犬は優れた嗅覚をもっていますから、トレーニングに色々な匂いを使用することで、特定の匂いと命令を結び付けられるようになります。
聴力の低下に気が付いたら、ある程度行動を制限する必要があります。慣れるまでは部屋の中でもリードでつないでおくのが安心です。敷地内のお庭であっても、リードにつないでおくかフェンスを作って、安全な環境で過ごせるようにしてあげてください。独りで歩き回らせるのは大変危険です。
万一に備えて、リードや首輪には連絡先や犬の耳が聞こえない(あるいは難聴である)ことを記載したタグをつけておきましょう。犬の居場所が把握できるように、猫のように鈴をつけるという方法もあります。マイクロチップが未装着の場合には、装着しておくとさらに安心です。
「びっくり」を和らげるようなトレーニング&配慮を
犬が聞こえづらくなると、人や他の犬などが近づいてくることに気が付きにくく、結果的に犬にとっては突然視界に入ってくる、突然触れられるといった状況になります。想像にたやすいですが、このような状況は非常にびっくりしますし、ときにはパニックになってしまうこともあるでしょう。このようなことにもトレーニングを行うことで、この反応を和らげることができます。健康的なおやつを使ったトレーニングで、犬のやる気を失わせずに頑張ってみましょう。色々な場所から犬の視界に入るように近づいて、近くまで来たときにおやつをあげることから始めてみます。続いて、寝ている犬を起こします。これは犬が非常にびっくりする状況です。そっと優しく起こすようにして、すぐにおやつをあげます。聴覚が低下した犬を起こす良い方法は、犬の近くを騒々しく歩いたり、ベッドを揺らす、あるいは眠っている犬の周りの床を優しく叩いたりして振動を起こして、それによって気配に気づいてもらうのがよいでしょう。
聴覚にトラブルをもつ犬を迎え入れるときは
今までご紹介してきたように、耳が聞こえない、あるいは難聴の犬でも、愛情をもって適切なケアを行うことで、問題なく日常生活を送ることができます。ただし、これは健常犬でも同様ですが、受け入れる前には、新しい犬のためにお家の準備を整えてください。聴覚にトラブルがある犬を飼うことに対して、事前に心構えや準備など必要な知識を調べて確認したり、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。また、その受け入れ予定の犬の状況についてもしっかり確認しておきます。迎い入れてからも、その犬の状況や性格に合わせたトレーニングが必要ですし、一筋縄ではいかないこともあるかもしれません。それでも、愛情と時間をかけることできっとうまく新しい生活に慣れて、いとおしい存在になっていくことでしょう。実際に、耳が聞こえないと、視覚や触覚などの別の感覚に頼ることになるので、必ず飼い主さんが見えるようにそばにいたり、安心するために飼い主さんに寄り添っていたりすることが多く、より一層愛らしく感じる場合もあるようです。耳が聞こえなくても、必ず愛情は届きます。積極的にコミュニケーションをとって人も犬も明るく楽しく過ごしましょう!


エリン・オリラは、言葉の力、そしてメッセージが対象とする読者に情報を伝え、さらには変革をもたらす力を信じています。彼女の執筆活動はインターネット上や紙媒体で展開しており、インタビュー、ゴーストライター、ブログ記事、クリエイティブ・ノンフィクションなど多岐にわたります。エリンはSEOとソーシャルメディアに関するあらゆる知識に精通しています。フェアフィールド大学でクリエイティブライティングの修士号を取得しています。Twitter(@ReinventingErin)で彼女に連絡するか、http://erinollila.com で彼女について詳しくご覧ください。
関連製品

免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート

【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

本来の免疫力を保ち、子犬の健康的な発育をサポート

犬に知られずにダイエットさせる
低カロリーのフードで、愛犬の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
犬に知られずにダイエットさせる
低カロリーのフードで、愛犬の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。








