
-
注目の製品
 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む -

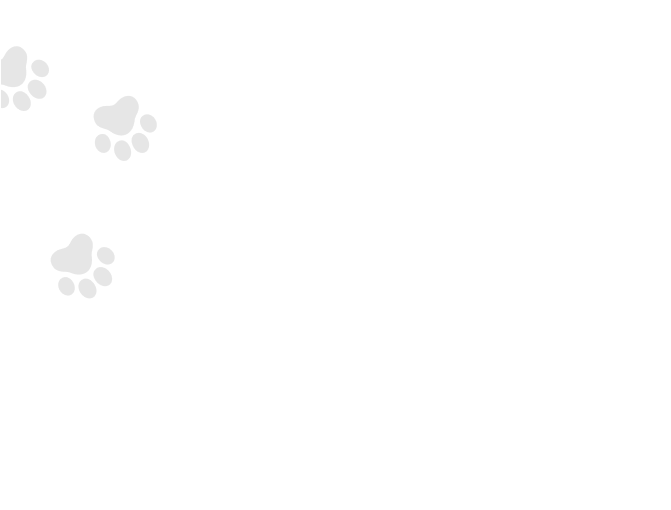
日頃から猫ちゃんにブラッシングしている、という飼い主さんは多いかと思いますが、では、歯のブラッシングとなるとどうでしょうか?猫に歯ブラシなんて考えたこともない・・・、という方も多いかもしれませんね。でも、歯周病をはじめとして猫の口腔トラブルは、猫の病気としてはよく見られるものの一つです。ですから、猫ちゃんにも歯と歯ぐきのケア は重要です。
猫の健康な口腔
まず、猫の口の中をチェックしてみましょう。口を開けてよく見られればそれが一番良いですが、慣れていなかったりすると難しい場合もあるので、その場合には無理せずに、猫が大きく口を開いたときか、猫の顔に触われればその時に、歯や歯ぐきの様子を確認してみましょう。ベッツウエスト動物病院によると、健康な歯ぐきは明るいピンク色です。猫の歯肉が鮮やかな赤色だったり、あるいは白っぽい、または黄色みを帯びているなどの場合は、口の中の炎症や貧血、肝疾患など深刻な健康トラブルが起きている可能性もあります。行動や外見のわずかな変化も見逃さないようにして、何か変わったことがあれば獣医師に診てもらってください。
歯が丈夫であることは、人間と同様にペットにとってもとても重要です。猫の永久歯は30本で、黄色または茶色のプラーク(歯垢)や歯石(硬くて鱗状の粘り気のある沈着物で、虫歯や口腔疾患の原因となる)が見られず、白色なら健康な状態と言えるでしょう。そして、猫の健康な舌はピンク色をしています。Cat Health には、ペットの舌が青白い場合、貧血を起こしている可能性があるので、直ちに動物病院を受診すべき、とあります。
猫の口臭についても考えてみましょう。フードを食べた直後に魚臭かったり、肉臭いといったことがあるかもしれませんが、時間が経って気にならなくなるようであれば、それはおそらく一時的なことで問題ないでしょう。もし、食事に関係なくニオイが気になり、さらに猫が顔を擦り寄せてきたときに、思わず鼻をつまんでしまうようなレベルなら、動物病院を受診して、しっかり口の中を確認してもらってください。
猫の歯みがきについて
歯の日常的なケアの方法としては、定期的な歯みがきをすることが口の中をできるだけ健康に保つためにもっとも有効な方法です。それは人間も犬も猫もみな同じです。とはいっても、猫に負担なく(嫌がらずに)、歯みがきを許容してもらうのはなかなか大変なことですよね。少しずつでもいいのでトレーニングを始めて、慣れて徐々にできるように頑張ってみましょう。
では、トレーニングは何から始めればいいでしょうか。アメリカ獣医歯科学会(American Veterinary Dental College)は、初めて口腔ケアを始めるペットオーナーには、とにかく焦らずゆっくり始めるようにアドバイスしています。まず、猫が口に触わられることに慣れるようにしてみましょう。毎日時間をとって猫の顔を優しく撫でて、唇をめくり上げて口の中を見てください。 それが平気になったら、指に少量のペット用の歯磨きペーストを付けて舐めさせます。猫用の歯磨きペーストはチキンやシーフード風味など猫が好むようになっているので、受け入れてくれることが多いです。次に、猫の歯を指で軽くこすってみてください。この感覚に慣れたら、実際の猫用歯ブラシを使ってみましょう。なお、猫の歯みがきには必ず猫用のグッズを使用してくだい。人間用のものには、人間には安全であっても猫にとって安全かどうかが分からない規格だったり成分が含まれている可能性があり、猫の健康に影響を及ぼす可能性があります。
このような習慣を身につけさせるのは、早ければ早いほどやりやすいので、年齢が若いうちにできるだけ早く始めましょう。子猫の性格にもよりますが、成長にともなって自我が確立すると、歯や歯ぐきのケアなどを含めた、"何かされること"を受け入れづらくなるかもしれません。そして、どんなにチャレンジしてもどうしても歯みがきを嫌がる猫ちゃんもいるでしょう。そのような場合には、猫用のマウスウォッシュやデンタルガム、 または口腔内のケアに役立つように特別に設計された製品を試してみるのもよい方法です。猫の息をリフレッシュさせ、プラークや歯石の沈着の軽減に役立ちます。
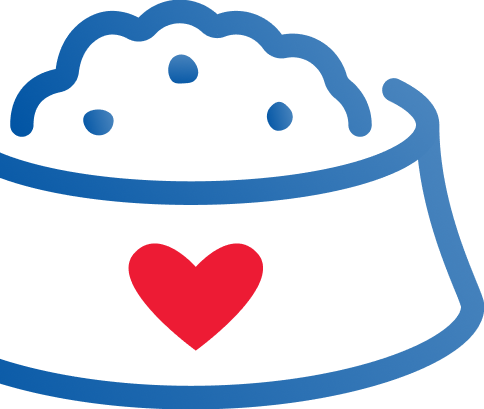

おいしいヒント
子猫は生後1年以内にワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成猫は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢猫や特別なケアが必要な猫はより頻繁な検診が必要になる場合があります。
獣医師によるクリーニング
人間の場合、ホームケアでカバーしきれない歯や歯ぐきのケアは、歯科を受診してやってもらうのと同じように、猫でも口腔内のしっかりとしたクリーニングを実施するには、動物病院を受診する必要があります。人間との違いは、猫の歯科処置は通常麻酔下で実施されることで、自宅での歯みがきでは届かない部分のプラークや歯石を除去します。ですから、この処置は猫ちゃんの口腔内の状態や健康状態全般など総合的に判断して、実施するかどうかを決めるもので、安易に実施できるものではありません。また、一度クリーニングしたからといって、永久にきれいなままということはなく、やはり日々のケアをしていなければ、またすぐに元の状態に戻ってしまいます。高齢になるほど口腔内のトラブルは増えるので、定期的な健康診断で口腔内もチェックしてもらいましょう。そのときどきの状況に応じて、処置が必要かどうかよく相談してください。
歯周病の精査のため、あるいは歯が折れたり抜けたりした場合には、歯の根元の状態を確認するために、レントゲン撮影を行う場合もあります。レントゲン撮影によって炎症の波及の程度や膿瘍の有無、歯や顎の骨の状態などが確認できます。こういった検査でも、麻酔処置が必要になることもあります。
猫の口腔内にトラブルがあるときの症状
多くの一般的な歯のトラブルでは激しい痛みがありますが、ベッツウエスト動物病院が指摘しているように、現代の猫の祖先となる野生の猫たちは、具合の悪い様子を示すと捕食者に襲われやすい、という状況におかれていたため、今の時代においても、ペットの猫は歯の痛みやその他の病気があるとき、それを隠そうとする という本能的な習性を残しています。
ハーモニー動物病院 によれば、口のニオイ(いわゆる口臭)は、猫に歯や歯ぐきのケアが必要であることを知らせる、もっとも一般的な手がかりです。そのほかの症状には以下のものがあります:
- 固形物を食べにくそうな様子がある、食欲が落ちる
- 口を気にするしぐさだったり、ヨダレが目立つ
- 歯肉の腫れや出血、膿などのトラブルがある
- 歯の変色
- 歯がぐらついたり、抜けたりする
- くしゃみや鼻水
口の中がよく見えなくても、こういった様子の変化があれば、口の中に問題がある可能性が高いため、かかりつけの獣医師に相談してください。
猫の口腔内トラブル
年齢とともに様々なトラブルが起きやすくなりますが、以下に猫で起こりやすい口腔内トラブルをご紹介します。
- 破折歯(歯が折れる):猫は年齢に関わらず、様々な環境や健康上の原因により歯が折れてしまうことがあります。獣医師は、その歯がどの部分で折れているか、折れてからどのくらい時間が経過しているかなどのほか、状況によっては歯の根元の状態やそのほかに肉眼で見えない異常がないかどうか、なども検査して確認することがあります。歯の治療については、専門的な機器が必要になることもあるので、そういった施設を紹介されることがあるかもしれません。
- 歯肉炎:歯ぐきの炎症は、プラーク中の歯周病細菌によって起こります。歯肉炎を治療しないままでおくと、さらに奥の方まで炎症が波及し、歯周病に進行する可能性があります。歯周病が進行すると歯ぐきだけではなく、歯の根元の骨までも破壊します。
- 歯の吸収病巣:これは、歯質が壊れて歯に穴が開いてしまうものです。コーネル大学猫医療センターによると、5歳以上の猫全体の3/4近くが罹患しているにもかかわらず、この歯の吸収の原因はわかっていません。この病気では、破歯細胞によって象牙質と呼ばれる歯の内部組織が壊され歯に穴が開き、進行すると歯が折れてしまいます。わずかな病変でも痛みがあり、食べ方や食欲に変化が起きたり、よだれや歯ぎしりといった症状が見られるようになります。
- 歯周炎:歯肉炎が進行した状態で、歯の周囲の靭帯や組織が後退して歯根を露出します。罹患した歯はしばしば抜歯が必要になります。
- 歯肉口内炎:歯周病による歯肉の炎症のほか、猫では口腔尾側粘膜(奥歯の奥や頬の粘膜を含む一帯)に左右対称に炎症が見られるのが特徴です。Veterinary Practice News は、この猫の歯肉口内炎は一般的に非常に強い痛みがあり、食欲低下から全く食べなくなってしまうこともあると紹介しています。よだれなどの口に関係した症状に加えて、体重減少や脱水など全身状態の悪化が生じることも多い病気です。直接的な原因は明らかではありませんが、ウイルス(FIV(猫免疫不全ウイルス)に感染している猫でしばしばみられます)や細菌、過剰な免疫反応など複合的な要因が関連していると考えられています。口の中が赤く腫れている、あるいは食べようとしたときに痛がって鳴く、などのようなことがあれば、すぐに動物病院を受診しましょう。
これらのようなトラブルに気づいたり、疑うような症状がある場合には、できるだけ早く受診して確認してもらいましょう。人間もそうですが、口の中のトラブルは痛みを伴うことが多く、食べられるかどうかに関わってくるので問題が深刻になります。このような症状に気づく前に、定期的な歯科検診を受けることは、その後の生涯にわたり健康な歯と歯ぐきを維持するのに役立つでしょう。


カレン・ルイス博士は、セントルイス近郊で動物にとってストレスの少ない動物病院を経営しています。犬や猫が最高の生活を送れるようサポートする傍ら、ブログ「VetChick.com」を運営し、受賞歴のある自然写真家としても活躍しています。
関連記事

猫の食性を理解して、理想的な食事回数を覚えておきましょう。また自動給餌器を利用する方法についても解説します。

トイレトレーニングをはじめ、様々なシチュエーションにあわせた愛猫のしつけにチャレンジする方も多いですよね。良い行いにはごほうびを与えるなど、トレーニングの目的にあわせた最適な方法をご紹介します。

ウェットフードは一般的に猫が好み、味にうるさい猫にはぴったりな選択肢になります。ウェットフードの利点や与え方について確認しておきましょう。

胃腸の弱い猫について、深掘りしていきます。このようなケースでの食事の役割について学びましょう。

猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。





