
-
注目の製品
 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む -

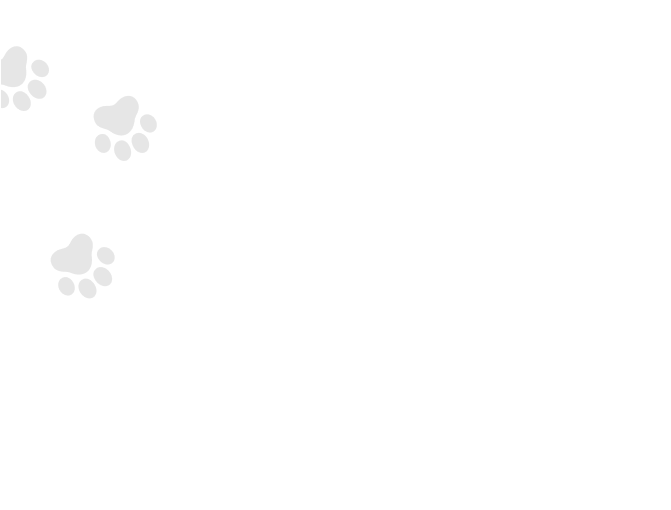
犬や猫にも尿が結晶化して石になってしまう尿石症(尿路結石症)という病気があります。人では上部尿路、つまり腎臓で結石ができそれが尿管に詰まってしまい、背中や腰に激しい痛みを起こす、といったことがよく知られていますが、犬や猫では、上部尿路よりも下部尿路である膀胱や尿道における結石のトラブルのケースの方が診察される機会が多いとされています。
尿中の結晶は、一般的には結石の前段階と考えられますが、実は犬や猫の尿中に結晶が観察されることは珍しいことではなく、結晶があるからといって必ずしも病的であるわけではありません。それは、尿中に見られる結晶にはいくつかの種類があり、その種類によって存在意義や解釈が異なるためです。今回はやや複雑ではありますが、この尿の結晶について解説してみたいと思います。

尿中の結晶はどのように形成されるのか
シンプルな考え方として、単純な食塩水を思い浮かべてみてください。溶液の中で溶解できる以上に物質が過剰になった場合、結晶が析出してきます。また、食塩水をコップに入れて放置した場合も、水分が蒸発して塩分が析出してくるでしょう。尿の結晶も原理は同じです。尿中の結晶の形成には、尿中に含まれる結晶成分の濃度、温度、尿のpHに左右されます。
実際の尿検査では、尿の保存状態によって結晶ができやすく変化していることもあるので、できるだけ新鮮尿で検査を行うことが理想的です。さらに、結晶の種類によってその性質が異なるので、結晶と尿の結石(尿石)とは必ずしもイコールではなく、結晶があるから尿石症、あるいはないからといって尿石症ではない、とも言い切ることもできません。つまり、尿石の種類によって、尿中に結晶が見つかったときに、尿石症のリスクが高いと考えられる場合と、そうとは言い切れない場合があるということです。
尿の結晶成分の種類によって、その作られ方、つまり原因が異なります。一般的には、腎臓から特定のミネラル成分が尿中に過剰に排泄される場合に結晶が形成されます。それ以外にも、肝疾患や中毒、遺伝性の病気などの理由で尿中に特定の成分が過剰に排泄されることがあります。
犬と猫での尿中の結晶の解釈の違い
犬でも猫でも尿中に見られる結晶の種類はほぼ同じです。ただし、一部の種類の結晶が認められた時に、猫では犬とは異なる解釈が必要な場合があります。
Wag!*¹ によると、犬の尿中の結晶には基礎疾患が関与していることがあり、泌尿器系以外の代謝性疾患を考慮する必要がある場合があるものの、結晶そのものが生体に悪影響を及ぼすことはあまりありません。一方猫では、特にオスは尿道が狭いため、結晶成分とほかの様々な物質が混じった状態のもの(尿道栓子)が尿道に詰まってしまい閉塞を起こしてしまうことがあります。
コーネル大学猫健康センター*² によると、猫の尿中の結晶は、猫の下部尿路疾患(FLUTD)と総称される尿路系の問題に関連していることがあるそうです。FLUTDの症状には次のようなものがあります。
- 血尿
- 排尿時にいきんでいる
- トイレ中に鳴く、叫ぶ
- いつもより尿量が少ない
- トイレ以外の場所で排尿する
これらの兆候に気付いたら、すぐに動物病院に連れて行きましょう。獣医師はまず膀胱に尿がたまっていないか確認すると同時に、必要な検査や処置を行います。尿検査では、成分検査と合わせて顕微鏡で結晶がないか確認し、必要に応じて血液検査やレントゲンの検査を実施します。
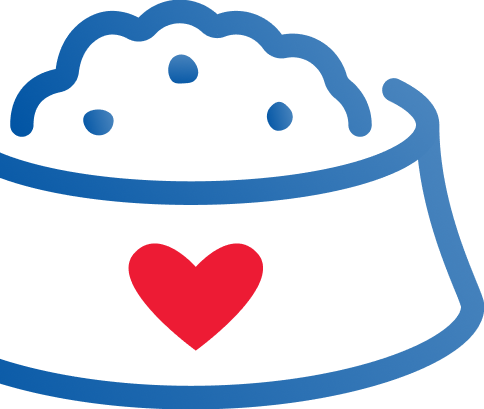

おいしいヒント
若いペットは、生後1年間はワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成犬のペットは一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢のペットや特別なケアが必要なペットは、より頻繁な検診が必要になる場合があります。
犬や猫で見られる尿中の結晶
犬や猫で見られる尿中の結晶の種類をご紹介します。
- ストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム):犬猫の尿中に頻繁に観察されます。酸性の尿で溶解しやすく、アルカリ性に傾いた尿や時間が経った尿で析出しやすい性質があります。犬では尿路の細菌感染による原因が最も一般的で、細菌感染がない場合には一時的なもので病的ではないことが多いと考えられます。一方、猫では細菌感染が無くても尿石が形成され、また前述のように尿道栓子を形成し、尿道に詰まって尿道閉塞を起こすことがあるため、注意が必要です。
- シュウ酸カルシウム:一度尿石ができてしまうと、溶解することができず、再発しやすいというやっかいな種類です。形成にいたる過程が複雑で完全には理解されていないため、まだ不明な点も多くあります。何らかの理由でカルシウムやシュウ酸が尿中に過剰に排泄されやすい、尿が酸性に傾きやすい、本来尿中に含まれている阻害因子が不足している、などの理由が考えられています。この結晶は正常な犬や猫ではあまり検出されることはありません。International Cat Care*³ によると、猫のエチレングリコール中毒について紹介しています。エチレングリコールは車の不凍液や古い保冷剤に含まれる成分で、猫が誤飲した場合致命的な腎障害を起こし、その際にはシュウ酸カルシウム結晶尿が認められるそうです。
- 尿酸アンモニウム:Vet Times*⁴ によると、この種類の結晶が観察される場合は肝疾患の可能性があります。またイングリッシュ・ブルドッグやダルメシアンは、遺伝的にこれらの結晶が形成されやすいことで知られています。猫ではまれですが、遺伝子の異常や欠損がある猫で観察されることがあります。
- シスチン:犬でも猫でも珍しい種類です。輸送系タンパク質の遺伝的な問題により過剰に尿中にシスチンが排泄されてしまうことで起こります。ミネソタ尿石センターによると、尿中の高いシスチン濃度は尿石形成の重要なリスク因子だとしています。
- ビリルビン:Lighthouse Veterinary Consultants によると、犬では健康であっても尿の濃縮に伴って認められることがありますが、猫のビリルビンが尿中に含まれることはありません。そのため、その際には肝臓や胆道系の異常が疑われます。
犬猫の尿石症および結晶尿の治療
尿検査で尿中に結晶が見つかった場合には、まずその種類の確認がなされます。さらに、尿石がすでにできていないか、泌尿器系以外の疾患がないかどうかも合わせて確認されるでしょう。結果次第では基礎疾患の治療の方が重要になることもあります。現時点で尿石が無くても、その後形成される可能性が疑われる場合には結晶の溶解や除去が優先されるでしょう。すでに尿石が形成されている場合には、その種類によって内科的治療、あるいは外科的な治療が選択されます。
結晶や尿石ができる原因はその種類によってさまざまなことは前述のとおりですが、治療後にこれらができにくいように尿の性状を維持していくのに、栄養は非常に重要な役割を果たします。獣医師は確認された結晶や尿石の種類に応じて、適切な療法食を推奨します。
同時に、尿が濃縮しないように、十分な水分摂取が必要です。新鮮な水をたっぷり用意し、いつでも飲める状態にしておきましょう。ウェットフードを取り入れることも、無理なく水分摂取量を増やすための良い方法です。
療法食の選択や給与方法、在宅時のケアについて獣医師の指示に必ず従いましょう。十分な水分補給と適切な栄養補給、こまめな尿のチェックをすることは、尿石症の予防に大いに役立ちます。
*参照先:
*1 https://wagwalking.com/condition/crystalluria
*2 https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/feline-lower-urinary-tract-disease
*3 https://icatcare.org/veterinary/resources/
*4 https://www.vettimes.co.uk/app/uploads/wp-post-to-pdf-enhanced-cache/1/management-of-common-uroliths-through-diet.pdf


パティ・クーリー博士は、受賞歴のある獣医師であり、その独自の思考、熱心なペット擁護活動、獣医職への情熱、そしてペットの健康に関する皮肉な記事で知られています。
クーリー博士は、ウェルズリー大学とペンシルベニア大学獣医学部を優等で卒業しています。また、名門のVMD/MBAデュアルディグリープログラムの一環として、ウォートン・スクール・オブ・ビジネスでMBAを取得しました。現在は、フロリダ州マイアミにある動物病院「サンセット・アニマル・クリニック」のオーナーです。
関連製品

免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート

【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

本来の免疫力を保ち、子犬の健康的な発育をサポート
関連記事

いつでもペットの健康状態を把握できるように、犬と猫の体温の測り方を知っておきましょう

犬や猫が新型コロナウイルスに感染するかどうかなど、感染について詳細に考えていきます。さらにコロナウイルスの種類について学びましょう。

ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。

ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。

ペットに知られずにダイエットさせる
低カロリーのフードで、ペットの体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なタンパク質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化物質、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
ペットに知られずにダイエットさせる
低カロリーのフードで、ペットの体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なタンパク質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化物質、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。




