
-
注目の製品
 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む -

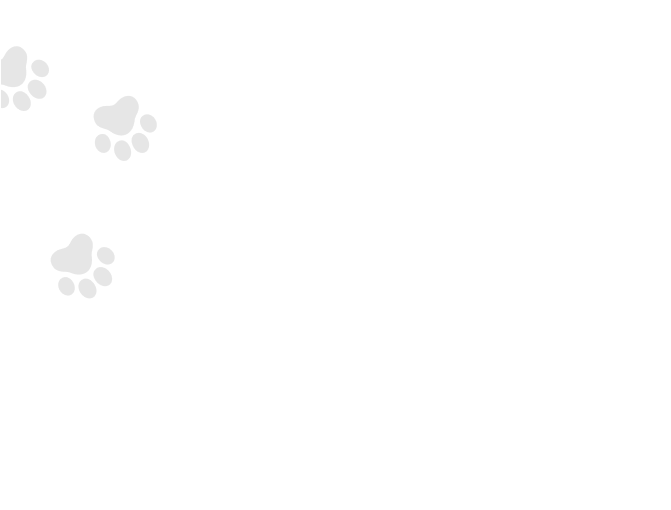
猫は毛づくろいをするため、時々毛玉を吐くのは生理的な現象と言えます。でも、繰り返し吐く、軟便になりやすい、などその頻度が高いときにはちょっと心配です。複数猫を飼っていたリすると、みんな同じものを食べているのに、特定の猫だけそういった頻度が高い、といったようなケースもあるかもしれません。これって、どういうことなのでしょうか。
胃腸が弱いとは?
胃腸が弱い、というと、実際には嘔吐や下痢といった症状を起こしやすいこと、を指しているものと解釈できます。猫だと毛玉の吐き戻しが特に異常なことではないので、嘔吐の頻度についての判断がしにくいかもしれませんが、単純な毛玉の吐き戻しであれば、何日もあるいは繰り返して体調が悪くなることはあまりありません。
胃腸が弱い、を深掘りする
私たち人間と同じように、猫でも特定の原因があるわけでもなくお腹の調子が悪くなることもあれば、体質的に胃腸が弱い、ということもあるかもしれません。でも、数日ごと、または数週間ごとに猫ちゃんが胃腸のトラブルを起こしているのであれば、まずは本当に医学的な問題がないのか獣医師に確認してもらう必要があります。よく外出する猫の場合には、そのような体調の変化が分かりにくいので、月に一度は自宅の体重計で、あるいは動物病院で体重を測るようにしてください。体重減少に気づくことは、猫の病気を早期発見するために非常に重要です。この習慣は、反対に体重の増加に気づくためにも役立ちます。
猫の胃腸の弱さに関連する原因
胃腸の弱い猫にみられる、一般的な原因
- 食物アレルギーまたは食物不耐症
- ストレス。これは特に猫では重要で、とりわけ多頭飼育で問題になりやすいです。ストレスは、人の過敏性腸症候群(IBS;Irritable Bowel Syndrome)の重要な要因の一つであり、猫にもこれと近いような状況が起こっているのかもしれません。これは現時点ではまだよくわかっておらず、あらたな研究が待たれます。
- 寄生虫
- 感染症
動物病院を受診するときは、可能であれば糞便検査のための便や、猫ちゃんの具合が悪い様子を撮影した動画を持参すると、非常に役立ちます。獣医師は状況に応じて、血液検査、糞便検査、超音波検査、X線検査などを実施します。場合によっては、生検が必要になることもあります。
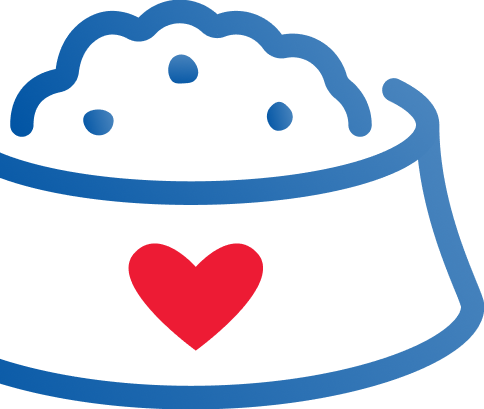

おいしいヒント
子猫は生後1年以内にワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成猫は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢猫や特別なケアが必要な猫はより頻繁な検診が必要になる場合があります。
胃腸の弱い猫の治療:食事について
根本的な原因が判明した場合には、その内容に基づいて治療が進められます。一方で、明らかな病的原因が見つからない場合には、まずは食事の変更を勧められる可能性があります。それは、胃腸の弱い猫の多くで、食事反応性腸症(FRE;Food Responsive Enteropathy)と呼ばれるケースがあるためです。その名のとおり、食事を変更することで症状が改善する消化器疾患の総称で、低アレルギー食や消化器系に配慮した食事への変更が推奨されます。もともと食べていたフードの何かしらの原材料が体に合わなかったり、脂肪の量がその猫ちゃんにとっては多かったなどのケースが考えられますが、はっきりとした原因はわからないことが多いでしょう。消化器系に配慮しているフードは、一般的に高品質で消化が良く作られており、炎症に対抗するためのオメガ3脂肪酸や、腸内細菌叢のバランスを改善するプレバイオティクスとなる優れた食物繊維源などが含まれています。
どの食事が合うのかは試してみないとわからないため、消化器系に配慮した食事で改善が見られない場合は、別のタイプを試すということになります。食物アレルギーや食物不耐症が疑われる猫の場合には、低アレルギー食を先に試される場合もあります。これらは除去食試験と呼ばれ、低アレルギー食のほか、その猫が以前に食べたことのない成分を主に含むフードを一定期間給与して、症状が改善するかを確認する方法です。低アレルギー食には、成分が厳密に限定されているものや、体がアレルゲンとして認識できないほど小さく分解されたタンパク加水分解物を含むものがあります。これらの除去食試験の最中は、獣医師から推奨されたフードだけを与えて、そのほかの食物は与えないようにすることが重要です。通常、胃腸に関する除去食試験の期間は2~4週間ですが、状況に応じて獣医師から指示があるでしょう。
可能であれば、ウェットフードとドライフードの両方を与えることを推奨します。というのも、胃腸トラブルの際には水分を喪失しやすく、脱水状態になりやすいためです。ウェットフードは猫に負担を与えずに水分摂取量を増やすことができ、かつ猫も好むケースが多く食欲を維持することもできるので、非常にメリットが大きいのです。なお、このような食事の変更は必ず獣医師の指示に従うようにしてくださいね。
監修:ハイン・マイヤー博士(DVM、PhD、Dipl-ECVIM-CA)


カレン・ルイス博士は、セントルイス近郊で動物にとってストレスの少ない動物病院を経営しています。犬や猫が最高の生活を送れるようサポートする傍ら、ブログ「VetChick.com」を運営し、受賞歴のある自然写真家としても活躍しています。
関連記事

トイレトレーニングをはじめ、様々なシチュエーションにあわせた愛猫のしつけにチャレンジする方も多いですよね。良い行いにはごほうびを与えるなど、トレーニングの目的にあわせた最適な方法をご紹介します。

猫の食性を理解して、理想的な食事回数を覚えておきましょう。また自動給餌器を利用する方法についても解説します。

猫の特徴的な食性や採食パターンを理解して、できるだけ消化器のトラブルが起きないようにするための食事の与え方や注意点などを学びましょう。

ウェットフードは一般的に猫が好み、味にうるさい猫にはぴったりな選択肢になります。ウェットフードの利点や与え方について確認しておきましょう。

猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。





