
-
注目の製品
-
注目の記事
 ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む -

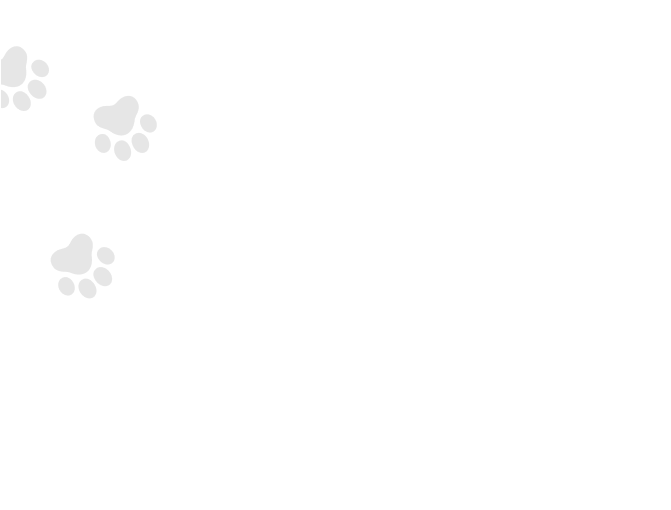
愛猫が痩せてきたら、心配になるものです。猫が痩せる原因は様々です。いずれにせよ、猫の体重減少は健康状態に問題があることを示しています。本記事では、猫が痩せる原因、痩せてきた場合に注意したい病気、太らせたいときの食事について詳しく解説します。
目次
うちの猫は痩せすぎ?適正体重?
猫の適正体重を見分けるのは難しく、 米国ペット肥満防止協会*¹によれば、多くの猫が太りすぎていると言われています。正常な体重の猫が痩せて見えることもあり、特に長毛種やお腹の垂れた品種では見極めが難しいことがあります。痩せているからといって、必ずしも動物病院に行く必要はありませんが、下記の方法を用いるなどして日々の体重管理はしっかり行うことが最善です。
猫が痩せすぎかチェックする方法
猫が痩せすぎているのかチェックする方法を紹介します。

ボディ・コンディション・スコアによる痩せすぎチェック
こちらは聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。これは、人間のBMI(Body Mass Index:カラダの大きさを表す指標)に相当するもので、獣医師はこのボディ・コンディション・スコア使って、動物の体重を評価します。ボディ・コンディション・スコア・チャートを使うと、愛猫が痩せすぎかどうかをチェックすることができます。チャートについては、アメリカ動物病院協会*²やWorld Small Animal Veterinary Community*³などのオンライン、またはかかりつけの動物病院に尋ねてみましょう。
ハンドテストによる痩せすぎチェック
これは、人間の手を物差しとして使って、猫のボディ・コンディションを確認する方法です。まずは猫の肋骨を触ってみましょう(前脚の後ろ側です)。ご自分の手の甲と同じような感触があれば、体重は適正です。肋骨が握りこぶしのような感触や見た目であれば、痩せている猫ということになります。肋骨が手のひらのような感触の場合は太りすぎだと考えられます。いかがですか?もしよくわからないようなら、 dvm360 がハンドテストを紹介しているこちらのビデオをチェックしてみてくださいね。
猫が痩せる原因
猫が痩せる原因には様々なことが考えられます。食事内容、ストレスなど精神面での影響や加齢などによって起こる変化が猫の体重減少につながることがあります。
猫の摂取カロリーが足りないことによる体重減少
適切な量の食事を猫に与えていないことで、必要な栄養やカロリーが摂取できていない可能性があります。または、猫は成長に伴い必要な栄養やカロリー量が変わってきますが、この変化に対応できる食事を与えていないなどが、猫が痩せる原因となることがあります。
猫の消費カロリーが増えることによる体重減少
猫の日々の運動量が増えると、消費するエネルギーが増えます。また、運動量が豊富な猫になるほど筋肉量が多く、基礎代謝量も多くなるため、それを踏まえたカロリー摂取が必要となります。運動量、基礎代謝を踏まえた食事を与えていないことも、猫が痩せる原因となることがあります。
猫がストレスを抱えることによる体重減少
猫はとてもデリケートです。環境などの変化が猫のストレスとなり食欲不振を招くことがあります。また、ストレスが原因となって胃腸の働きに影響を与えると、嘔吐や下痢につながり猫が痩せることがあります。
加齢に伴う消化機能の低下による体重減少
加齢に伴う消化機能の低下によって栄養を十分に吸収できなくなることが猫の体重減少を招くことがあります。これは、10歳齢を超える高齢の猫によく見られる現象なので、高齢期に入った、または近い猫がいる場合は注意しましょう。
「 高齢猫のフードについて気を付けること」もご参考ください。
猫が痩せてきた場合に潜む危険な病気
猫が痩せてきた場合、危険な病気の徴候であることがあります。猫の体重減少で気をつけたい病気について紹介します。
腎臓病
最近の研究によると、猫の腎臓病では、体重減少がごく早期の段階の徴候であり、腎臓病と診断されるより3年も早く現れ始めることがあるとされています。早期の介入は、早く治療を始めることができるチャンスとなります。最近猫が痩せてきたなと気になる方は、かかりつけの獣医師の診察を受けるようにしましょう。
「 猫の腎臓病の症状や食事療法」もご参考ください
糖尿病
糖尿病を患っている場合、体内のブドウ糖(血糖)をエネルギーとして利用しにくくなります。そのため、猫の身体は脂肪やたんぱく質をエネルギー源として代替するようになり、体重減少を招くことがあります。
上記以外にも、歯や口内の問題、消化器系の疾患やがんなどによって体重が減ることもあります。猫が痩せぎみだからとって、必ずしも病的で医学的な緊急事態というわけではありませんが、愛猫の体重減少について心配なことがあるときには、かかりつけの獣医師の診察を受けるようにすることが大切です。
一方で、愛猫が痩せているかどうかに関わらず、食事をまったくとらない場合、それは医学的な緊急事態です!その場合は、直ぐに猫を動物病院に連れて行ってください。猫が数日間食事を取らないと、肝リピドーシス、あるいは脂肪肝症候群として知られる、命に関わる状態に陥る可能性があります。
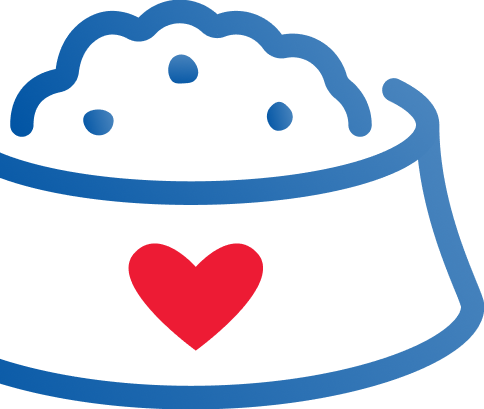

おいしいヒント
子猫は生後1年以内にワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成猫は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢猫や特別なケアが必要な猫はより頻繁な検診が必要になる場合があります。
猫を太らせたい場合の食事とフード

飼っている猫が痩せていて、もっと太らせたいと思っている場合、まず獣医師に診てもらって、何らかの基礎疾患の可能性を排除するようにしましょう。健康上の問題がないことが分かったら、以下に紹介する猫の体重減少を改善する食事のヒントを参考にしてみてください。
猫の食事量を増やして太らせる
健康だけど痩せている猫を太らせたい場合、単純に1日当たりの食事の量を増やすか、自由にドライフードを食べられるようにしてあげる方法があります。猫は1日を通して食事を「分けて」食べたり、好きなタイミングで少量ずつ食べたりすることを好むため、1日中食事を取れるようにすることで食べる量に大きな違いが生まれることがあります。この方法がその猫に適しているかどうか、かかりつけの獣医師に確認してみましょう。食事を自由に摂取させる方法は肥満につながる可能性があるため、猫の食事の与え方全般として推奨されるわけではなく、特定の状況でのみ推奨されます。
猫を太らせたいけど食事を食べないときの対処
- 複数の猫を飼っている場合、1頭が食物を見張っていて、他の猫が十分食べられないようにしている場合があります。1日中、すべての猫が安心して、脅威を感じずに食事が取れるような環境づくりを目指しましょう。
- 神経質な猫の場合、食事を与える場所は、稼働しているエアコンや空気清浄機、吠える犬など、猫にとって不快な音が出たりして脅威となるものの近くは避けるようにします。
- 猫に普段ドライフードだけを与えている場合は、ウェットフードを追加して与えてください(逆の場合も同様)。
- 猫の性格にもよりますが、自分のペースで静かに食事をしたいタイプの子もいます。食事の時間になると、猫をかまってずっと猫のことを見ている方もいますが、それであまり食べてくれないのであれば、静かな場所で食事を与えるようにして、あまりかまいすぎないようにしてみてください。
- 選り好みが激しい猫の場合、フードのフレーバーを変えたり、ずっと与えていたドライフードやウェットフードを変えたりしてみてください。ムースタイプの食感が好きな猫もいれば、シチュータイプが好きな猫もいます。ただし、フードを切り替える際は、消化不良を起こさないように少量ずつ試すなど注意しながら行うようにしましょう。
- 匂いは、食欲を刺激します。電子レンジで少しウェットフードを温めると、匂い立ちがよくなり嗜好性が高まります。その際には、電子レンジに対応している適切な容器を使用するようにして、温めすぎないように注意しましょう。
- 細かく刻んだローストチキンなどのトッピングを利用する方法もあります。もちろん、このようなトッピングは非常に少量にします。多くの猫は、ローストチキンの匂いや風味を好みます。必ず皮を取り除いた肉の部分を与えてください。猫に毎日与える基本的な食事は、バランスの取れたキャットフード(総合栄養食)にしましょう。
- キャットフードに、ごく少量のツナの缶詰の汁や食塩無添加のチキンスープを加えてみるという方法もあります。ただし、使用するときには、塩分や油分に注意しましょう。
回復期、高齢期の猫を太らせたい場合の対処
病気の回復期など、少量で高い栄養を賄うことのできる、高カロリーの療法食(ウェットタイプ)が体重減少に有効なケースもあります。また、高齢で体重を維持することに苦労している猫の場合は、酸化防止成分やオメガ-3、-6脂肪酸およびプレバイオティクスを豊富に含む消化しやすいフードが体重維持、または太らせたい場合に効果的なことがあります。愛猫に健康上のトラブルが見つかった場合には、担当獣医師が、その猫の治療のためになるフードをを勧めてくれることでしょう。
「高齢猫のキャットフード」に関する記事もご参考ください。
猫のフードを変更したり、栄養サプリメントを与えたりする前には必ず担当の獣医師に確認しておきましょう。
お家の猫が痩せすぎているかもしれないと心配になったら、まずは担当の獣医師に相談しましょう。獣医師は、体重が減少するような病的な原因がないかを確認した上で、その猫の食事量を増やすのにどの方法がベストなのかを選択するアドバイスをしてくれます。猫ちゃんが健康な体重にもどるのももう間もなくでしょう!
「愛猫の体重管理」についての記事もご参考ください。
参照先:
*1 https://www.petobesityprevention.org/2022
*2 https://www.aaha.org/globalassets/02-guidelines/weight-management/weightmgmt_bodyconditionscoring.pdf
*3 https://wsava.org/


サラ・ウーテン博士は、2002年にカリフォルニア大学デービス校獣医学部を卒業しました。アメリカ獣医ジャーナリスト協会の会員であるウーテン博士は、コロラド州グリーリーでの小動物診療、関連分野、リーダーシップ、クライアントとのコミュニケーションに関する講演、執筆活動に携わっています。家族とのキャンプ、スキー、スキューバダイビング、トライアスロンへの参加を楽しんでいます。
関連記事

胃腸の弱い猫について、深掘りしていきます。このようなケースでの食事の役割について学びましょう。

猫の食性を理解して、理想的な食事回数を覚えておきましょう。また自動給餌器を利用する方法についても解説します。

ウェットフードは一般的に猫が好み、味にうるさい猫にはぴったりな選択肢になります。ウェットフードの利点や与え方について確認しておきましょう。

トイレトレーニングをはじめ、様々なシチュエーションにあわせた愛猫のしつけにチャレンジする方も多いですよね。良い行いにはごほうびを与えるなど、トレーニングの目的にあわせた最適な方法をご紹介します。

猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。








