
-
注目の製品
 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む -

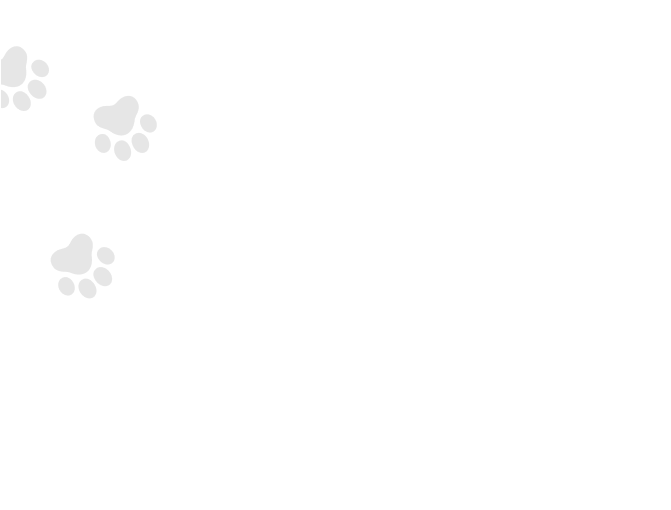
普段何気なく見ているものでも、その中に血のようなものが混じっていたら、それはびっくりしますよね。便に血が混じった状態が血便ですが、便の状態(下痢なのか正常便なのかなど)、色や量、混ざり方などによって考えられる状況はさまざまです。特に心配する必要がない場合もあれば、中には緊急性を要するケースもあります。心配なことがあれば、基本的には動物病院に受診いただくことが前提ですが、事前に知っておきたい犬の血便に関する原因や、注意すべき状況についてご紹介します。
犬の血便の原因
- 大腸炎。大腸が何らかの原因で炎症を起こした状態で、犬では比較的よく見られます。頻繁に便意をもよおし力む様子が見られ、ゼリー状の粘液の混じった下痢や軟便が見られることが多く、ときに血液が混じることもあります。人の食べ物をイタズラしたりなど、普段食べ慣れないものを食べたりすることで起こることが多いですが、別の原因が潜んでいることもあります。
- 犬パルボウイルス感染症などの感染症や急性出血性下痢症候群など。重度の出血性の下痢症状が急激に見られ、短期間に非常に深刻な状態に至る可能性があります。パルボウイルスについてはワクチン接種による予防が大切です。
- 異物の摂取。異物の内容にもよりますが、骨や砂利などの鋭利な形状の場合、腸管壁が傷つき、出血してしまう場合があります。
- 慢性の腸疾患。食事を変更することで改善する食事反応性腸症や抗菌薬によって改善する抗菌薬反応性腸症などがあります。
- 寄生虫。消化管の寄生虫によって粘膜が傷つき出血することがあります。かかりつけの獣医師の指示に従って、駆虫プログラムを実施してください。
- 腫瘍や(非腫瘍性の)ポリープ。
- 食物アレルギーや食物不耐症。
- 毒物。殺鼠剤などの一部の毒物は、腸管を含む全身の出血を引き起こします。
ここまで、犬の血便の際に考えられる原因を紹介しました。では、すぐに動物病院に受診すべきなのは、どんな状況でしょうか。
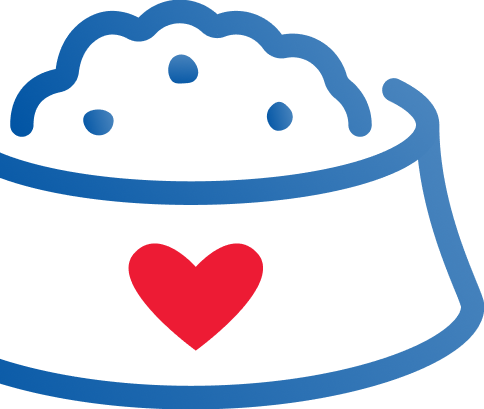

おいしいヒント
子犬は生後1年間、ワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成犬は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢犬や特別なケアが必要な犬は、より頻繁な検診が必要になる場合があります。
注意すべき状況とは?
わずかな血液が糞便中に混じっていた場合、元気や食欲があって、嘔吐や下痢などの症状が無ければ、少し様子をみてもおそらく問題はないでしょう。一方で、様子を見ることはせずにすぐに動物病院の受診が必要なケースもあります。
- 重度の下痢の場合。出血の有無にかかわらず、形がほとんどない水様便が見られるほどの場合には、かなり腸の機能が低下してしまっています。さらに嘔吐の症状もあれば、急激に脱水状態に至る可能性があります。加えて便に血液が混じっているとなれば、さらに事態は深刻です。なお、愛犬がワクチンを接種していない、あるいは接種歴が不明な場合には、かかりつけの獣医師にその旨を伝えるようにしてください。感染症の疑いがある場合には、治療にあたってさらに配慮する必要があるためです。
- 元気や食欲が低下している場合。下痢の状態がそこまでひどくなくても、元気や食欲が落ちているようなら早めに動物病院を受診してください。犬が元気で、普段と変わらず食べたり遊んだりしていれば、1~2日程度待ってみて、様子を見てもいいでしょう。
- 血便が続く場合。犬が元気で調子がよさそうに見えても、1日に何度も血便をする、あるいは連日続く、という場合には獣医師の診察が必要です。
- 思い当たることがあるとき。血便が出るタイミングの少し前に、犬がゴミ箱をイタズラした、あるいは骨を食べてしまった、犬が何らかの毒物や薬物を口にしたかもしれない、というような出来事があった場合も、まず獣医師に相談することをお勧めします。必要な検査を行うことで、症状がひどくなる前に対処できる可能性もあります。
動物病院を受診する際には、糞便検査用のサンプルとして少量の便を採って持参すると非常に役立ちます。また、排便時の様子や便の状態を撮影して獣医師に見てもらうことで、より症状や状況が伝わり診断に役立つ場合もあります。
獣医師は、動物の状態や状況に応じて血液検査や画像検査(レントゲン検査や超音波検査など)を行います。数日間必要な治療を行い、消化の良い回復期用フードなどを給与することで、回復することも多いと思います。それでも症状が続く場合には、腫瘍や炎症性腸疾患などを疑い、生検などの精査を提案されることもあります。
いずれにしても、愛犬について何か気になる場合には、早めにかかりつけの獣医師に相談してみましょう。転ばぬ先の杖ですね!
監修:ハイン・マイヤー博士(DVM、PhD、Dipl-ECVIM-CA)


カレン・ルイス博士は、セントルイス近郊で動物にとってストレスの少ない動物病院を経営しています。犬や猫が最高の生活を送れるようサポートする傍ら、ブログ「VetChick.com」を運営し、受賞歴のある自然写真家としても活躍しています。
関連製品

免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート

本来の免疫力を保ち、子犬の健康的な発育をサポート

【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート

犬に知られずにダイエットさせる
低カロリーのフードで、愛犬の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
犬に知られずにダイエットさせる
低カロリーのフードで、愛犬の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。








