
-
注目の製品
 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む -

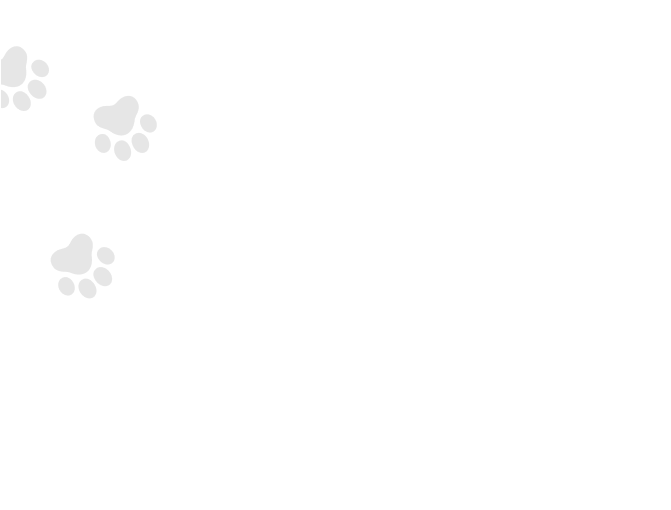
人でも猫でも一般的に、体重チェックというと体重が増えてしまうことに注目が行きがちですが、その反対にとくに減量などをしているわけではないのに体重が落ちてしまう、いわゆる原因不明の体重減少は、何らかの病気の徴候である可能性もあり、非常に重要です。たかが体重・・・ではないのです。
体重モニタリングの重要性
体重測定は自宅でできるもっともシンプルでわかりやすい健康チェックの方法です。はっきりとした数値で体重の増加や減少を判断できるため、その変化にいち早く気づくことができます。猫は具合の悪さを隠すのが上手なので、体調不良の徴候に飼い主さんが気づくまでに実は病気がかなり進行してしまっている、ということもあり得ます。定期的に体重のモニタリングをしていれば、その変化に早い段階で気づくことができ、その分早く対処することができます。
その理由が、単に新しいフードが気に入らず、体重が減った(あるいはその逆の理由で増えた)ということで、とくに病的な問題がなかったとしても、その体重の増減そのものが猫の健康に影響を及ぼすこともあります。
無理なく体重測定を習慣化できるように、小さいときから慣らしておきましょう。もちろん、動物病院でも体重測定をしてもらえます。動物病院に慣れるという意味でも、定期的に体重測定のために動物病院に立ち寄ってもいいかもしれませんね。
自宅での体重測定の方法にはいくつかありますが、おっとりタイプの猫さんなら、体重計に乗せるだけで測れます。もしくは、なにかカゴのようなものに入れて重さを測り、あとからカゴの重量を差し引いてもよいでしょう。抱かれるのが平気なら、抱っこしたまま体重計に乗り、自分の体重を差し引くという方法もあります。いずれにしても、これをお決まりのルーティーンにしておけば、猫も特段嫌がるということはないはずです。体重測定の頻度としては、子猫の間は2週間ごと、成猫になったら1か月ごとが適当でしょう。
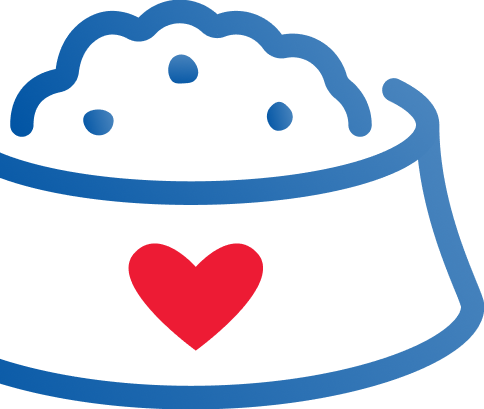

おいしいヒント
子猫は生後1年以内にワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成猫は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢猫や特別なケアが必要な猫はより頻繁な検診が必要になる場合があります。
猫の体重減少の原因
猫の体重が減少する原因は複数あります。猫でよく知られているケースを紹介します。
腎臓病:高齢の猫に多い病気です。その最も早期の徴候の一つに体重減少があります。普段より多く水を飲んでいることや食欲がイマイチであまり食べていないことで飼い主さんが気づくこともあります。
寄生虫:最近では大量の寄生虫がいることは珍しいとはいえ、それでも寄生虫が体重減少の潜在的な原因になっているケースもあります。寄生虫の診断がなされたら、猫の年齢やライフスタイルに合わせた寄生虫予防策を獣医師と相談しましょう。屋外に出て狩りをしてくる場合には、より頻繁な投薬が必要ですし、根本的に飼育方法を見直す必要があるかもしれません。
甲状腺機能亢進症:これは中年以上の猫に多い病気で、甲状腺ホルモンが過剰になることで代謝が高まります。猫は異常なほどよく食べるにもかかわらず、体重は減っていきます。甲状腺機能亢進症の猫は異常に活発なことが多く、攻撃的になることもあります。
がん:痛みなどの明らかな症状がなく、見つけるのが難しいケースが多くあります。体重減少は最も一般的な最初の徴候であり、飼い主さんが気づける唯一の徴候かもしれません。
胃腸障害:慢性腸症や食物有害反応などの消化器疾患は、猫が食物から必要な栄養素を十分に取り入れられないため、体重減少を引き起こす可能性があります。
糖尿病:肥満は糖尿病の重要なリスク因子として知られていますが、一方で糖尿病になってしまった後は、体重減少が最も一般的な徴候の一つとなります。
歯と口の痛み:実は思っている以上に猫の歯科疾患は存在しています。口の中や歯茎に痛みがある猫は、だんだん食べなくなって体重が減ってしまいます。
ストレス:同居猫と折り合いが悪い、など常に居心地が悪く解消されないストレスが続くと、食欲に影響し食事量が減ってしまうケースがあります。
猫の体重の把握の重要性がご理解いただけたでしょうか。正常時の体重を知っていれば、その変化に早く気づき、適切な対処をすることができます。意図しない体重減少に気付いたら、すぐに動物病院を受診するようにしてください。獣医師は状況に応じて血液検査や尿検査など必要な検査を行うこともあります。体重も含め、普段から猫ちゃんの様子をよく観察するようにしてくださいね。
監修:ハイン・マイヤー博士(DVM、PhD、Dipl-ECVIM-CA)


カレン・ルイス博士は、セントルイス近郊で動物にとってストレスの少ない動物病院を経営しています。犬や猫が最高の生活を送れるようサポートする傍ら、ブログ「VetChick.com」を運営し、受賞歴のある自然写真家としても活躍しています。
関連記事

ウェットフードは一般的に猫が好み、味にうるさい猫にはぴったりな選択肢になります。ウェットフードの利点や与え方について確認しておきましょう。

胃腸の弱い猫について、深掘りしていきます。このようなケースでの食事の役割について学びましょう。

トイレトレーニングをはじめ、様々なシチュエーションにあわせた愛猫のしつけにチャレンジする方も多いですよね。良い行いにはごほうびを与えるなど、トレーニングの目的にあわせた最適な方法をご紹介します。

猫の食性を理解して、理想的な食事回数を覚えておきましょう。また自動給餌器を利用する方法についても解説します。

猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。





