
-
注目の製品
 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 室内小型犬 避妊・去勢後 1歳以上 成犬用
室内小型犬 避妊・去勢後 1歳以上 成犬用
避妊・去勢後の体重管理と室内犬の健康をマルチサポート
今すぐ購入 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む -

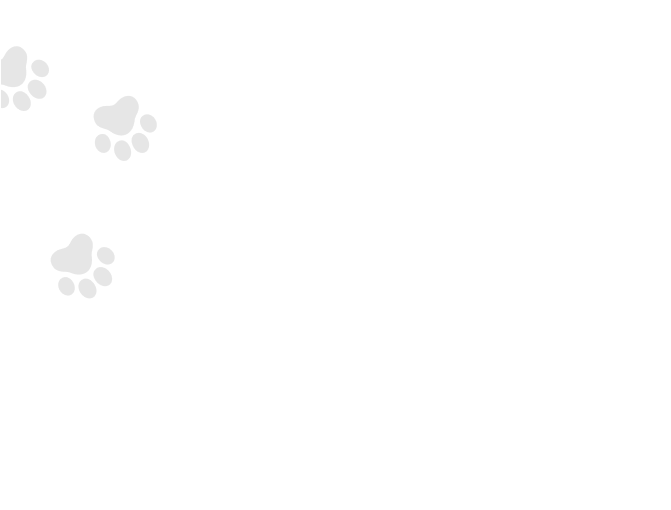
自由気ままな象徴のイメージのある猫ですが、実は人間と同様に便秘になることがあります。おそらく気持ちのいいものではないはずですが、猫がそれを直接訴えてくることはまずないので、こちらから気づいてあげる必要があります。そうはいっても、猫のお腹の不調はどうやったらわかるものなのでしょうか。猫の便秘の原因と注意したいサインについて解説していきます。
便秘とは?
便秘とは、排便回数が低下し、乾いて硬くなった便が腸内に停滞して排便しづらくなった状態です。排便していない、便が小さい、便が出にくそうなどのほか、食欲低下や嘔吐等の症状が見られることもあります。便秘が続くと脱水症状や痩せてくるなど、全身状態が悪化していくようになります。猫の便秘は安易に放置してはいけません。
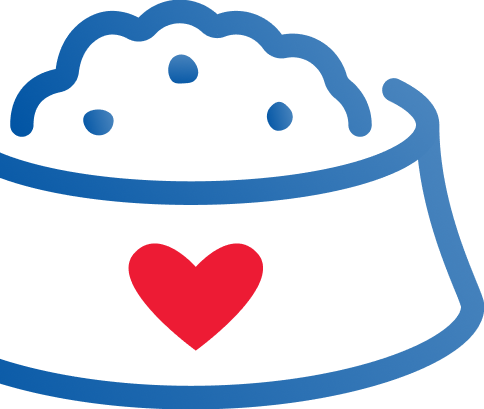

おいしいヒント
子猫は生後1年以内にワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成猫は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢猫や特別なケアが必要な猫はより頻繁な検診が必要になる場合があります。
猫の便秘の原因
基本的に猫は犬ほど飼育するのに手間のかからない動物ですが、それでも個々の猫にはそれぞれ性格や体質があり、それぞれに合った暮らしができる環境づくりは大切です。便秘の原因にはこのような日々の暮らしや食生活に関連していることも多くあります。
水分不足:猫は砂漠で生活していた祖先をもち、少ない水分で生きられる能力をもっていますが、その反面、水をあまり飲まない傾向があります。結果として、水分不足になりやすく、便が硬くなりやすい可能性があります。
さらに多頭飼育の場合、食事や水が平等に行き渡らなかったり、猫同士の相性が悪くて飲みたいときに水を飲めない、という状況が起こることもあるかもしれません。猫が水分不足にならないように、複数の水飲みボウルを家のあちこちに置いて、猫がどこにいても自由に水を飲めるようにしておきます。最低でも、家にいる猫の数よりも1つ多い水飲みボウルを用意しましょう。
食生活では、ドライフードのみを与えられている場合、結果的に水分不足により便秘になってしまうこともあります。パウチや缶詰などのウェットフードを利用することは、より簡便に無理なく猫の水分摂取量を増やすベストな方法です。
グルーミングによる被毛の飲み込み:きれい好きな猫は、起きている時間の約30~40%をグルーミング(毛づくろい)に費やしています。毛玉として吐き出す場合もありますが、猫によっては腸にとどまって便秘の原因となることがあります。
けがや痛み:骨盤骨折は猫の交通事故などで起こりやすいけがです。大腸の位置に影響し、結果的に便の通路を物理的に狭めて通過しにくくしてしまうことがあります。また、高齢に伴って関節のこわばりなどが出てくると、排便のためにしゃがむ姿勢が苦痛に感じるようになるかもしれません。このようにそもそも排便しようとする回数が減ってしまうことで便秘になってしまうこともあります。
腫瘍:腸の領域に腫瘍ができると、外側から腸を圧迫したり、内側でスペースを奪ったりすることによって、便の通過を妨げることがあります。
神経の問題:腸の内容物は、蠕動運動と呼ばれる筋肉の収縮によって一方向に送られます。これは自動的に行われ、意識してするものではありません。ところが一部の猫では、神経の問題によってこの収縮がうまくできないことがあります。シャムを含むいくつかの品種にはこの傾向があるといわれています。猫では便秘が慢性化し、巨大結腸症という病態に至ることがありますが、この神経の問題との関わりも深いと考えられています。
消化管以外の病気:腸のこととは直接関連のないように見える、たとえば腎臓病などの病気でも、水分不足(脱水症状)により便秘になりやすいことが知られています。
肥満と運動不足:運動は腸の動きを刺激し排便を促すのに効果的です。肥満の猫の多くは運動不足なケースが多く、内臓脂肪も便通に影響を与えている可能性もあります。
猫の便秘をチェックする方法
嘔吐や下痢など明らかな症状があるのとは違って、猫の腸の動きが悪いことを確認するというのはなかなか難しいことです。何日出ていないから、などの明確な定義があるわけではないので、以下のようなポイントをよく観察する必要があります。
注意すべきポイント:
まずは猫のトイレをよく確認します。排便の回数と便の硬さの変化に注意してください。トイレチェックをして掃除をあまりしなくてもよくなったり、便の大きさや外観がいつもと違っている場合(硬い、もろい)、便通が滞っているサインかもしれません。
排泄時の様子にも注意してください。いきみや鳴き声などを出していないか、またはトイレに長くいるにもかかわらず便が出てない、といった様子に気づいたら、できるだけ早く獣医師に診てもらう必要があります。これは膀胱炎や尿道閉塞でも似たような症状のため、医学的な緊急事態のサインである可能性もあります。
トイレ以外の排便に注意してください。痛みがあってトイレまでたどり着けない、トイレが使いにくい等の場合、実は排便を我慢していて便秘気味になっている可能性があります。
何となくいつもの元気がない、覇気がない、という様子はありませんか。排便というキーワードにつながる症状が何もなく、体調が悪そうに見えることだけが唯一のサインであることもあります。無気力で、遊びや同居の猫にも無関心な様子にみえるかもしれません。
猫は調子の悪さをできるだけ隠そうとします。ですから日頃からその様子をよく観察して、いつもと違う様子があれば、必ず獣医師に相談するようにしてください。便秘の場合はとくに早期に対処することが非常に重要です。キャットフードの内容を変更したり、水分摂取の方法を工夫することで改善が見られる場合もあります。慢性化してしまうと、腸の本来の働きが失われてしまい、内科的な方法では治療が難しくなってしまうケースもあるからです。人間も猫もお互いに"すっきり"して毎日を過ごしたいものですね。
監修:ハイン・マイヤー博士(DVM、PhD、Dipl-ECVIM-CA)


カレン・ルイス博士は、セントルイス近郊で動物にとってストレスの少ない動物病院を経営しています。犬や猫が最高の生活を送れるようサポートする傍ら、ブログ「VetChick.com」を運営し、受賞歴のある自然写真家としても活躍しています。
関連記事

トイレトレーニングをはじめ、様々なシチュエーションにあわせた愛猫のしつけにチャレンジする方も多いですよね。良い行いにはごほうびを与えるなど、トレーニングの目的にあわせた最適な方法をご紹介します。

胃腸の弱い猫について、深掘りしていきます。このようなケースでの食事の役割について学びましょう。

猫の食性を理解して、理想的な食事回数を覚えておきましょう。また自動給餌器を利用する方法についても解説します。

ウェットフードは一般的に猫が好み、味にうるさい猫にはぴったりな選択肢になります。ウェットフードの利点や与え方について確認しておきましょう。

猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。





