
-
注目の製品
 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む -

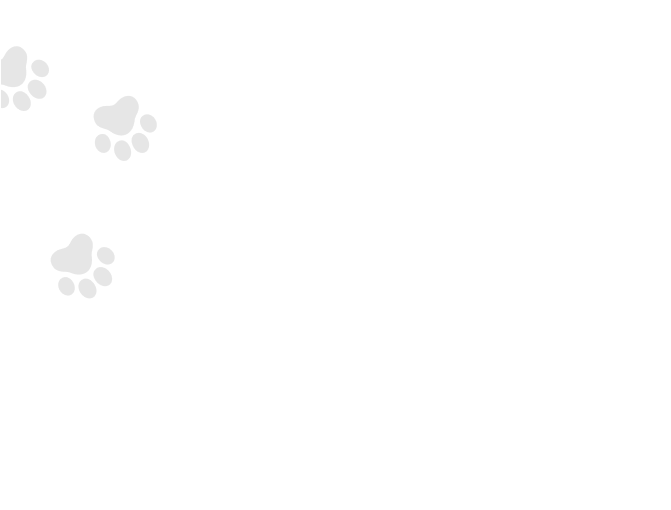
猫のお腹がたぷたぷ、あるいはパンパンに膨れていると感じたことはありませんか?このような状態は「腹部膨満」と呼ばれ、さまざまな原因が考えられます。今回は、猫のお腹が膨らむ主な原因や、必要な検査・治療についてわかりやすく紹介します。
猫のお腹がたぷたぷと膨らむ原因は?
猫のお腹がたぷたぷと膨らんでいる場合、肥満によることもありますが、腹水が原因である可能性もあります。腹水は悪性腫瘍や心不全など、重篤な病気のサインである場合があるため、注意が必要です。
肥満
見た目にはゆっくり揺れるような柔らかいふくらみであることが特徴な膨らみの場合、肥満が主な原因と考えられます。特に避妊・去勢手術後の猫や運動量が少ない猫では、下腹部に脂肪がたまりやすく、皮膚や脂肪が揺れるようにたるんで見えることがあります。
また、加齢による筋肉の衰えや皮膚のたるみでも、同じようにお腹が下がってたぷたぷして見えることがあります。
腹水
猫のお腹に水(腹水)がたまると、膨らんでたぷたぷとした感触になります。触ると中身が動くようなら、腹水の可能性があり、以下のような疾患が原因となっている可能性があるため注意が必要です。
- 出血:腹腔内への出血は、腫瘍からの出血、内臓の損傷、血小板数減少または血小板機能異常症、抗凝固性殺鼠剤の摂取などから起こります。
- 悪性腫瘍(がん):悪性腫瘍は、体液や場合によっては血液の腹腔内貯留を引き起こすことがあります。
- 心不全:右心不全があると、効率的に血液を送り出すことができなくなり、その結果として腹水が溜まることがあります。心不全が疑われるときは緊急事態と考えて、直ちに検査を受ける必要があります。
- 低たんぱく血症:血液中のたんぱく質が不足することで起こり、肝不全・腎臓病・腸の疾患・栄養不良などが原因になります。たんぱく質が極端に減ると、水分が血管外に漏れやすくなり、腹水やむくみが生じることがあります。
- 猫伝染性腹膜炎(FIP):FIPは猫で腹水を起こす代表的な疾患で、猫コロナウイルスが原因のウイルス性疾患です。決定的な治療法や予防法が確立されておらず、現在の獣医療では完治が難しい病の1つです。
- 臓器の破裂:膀胱、胆嚢、消化管などの破裂は、内容物が漏れ出すことがあり腹水の原因となります。いずれも緊急を要する病態です。
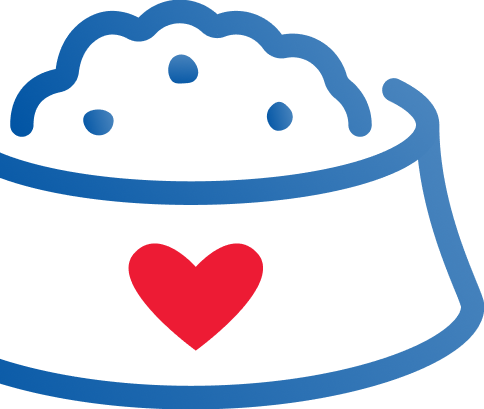

おいしいヒント
子猫は生後1年以内にワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成猫は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢猫や特別なケアが必要な猫はより頻繁な検診が必要になる場合があります。
猫のお腹がパンパンに膨らむ原因は?
猫のお腹がパンパンに膨らんでいると、臓器拡張、寄生虫、腫瘍などさまざまな原因が隠れている可能性があります。
臓器膨張
臓器が大きくなることによって、猫のお腹がパンパンに膨らむことがあります。腹部膨満を引き起こす可能性のある猫の臓器は、以下の通り複数存在します。
- 肝臓、脾臓、腎臓:感染症や炎症、他の病気への反応、腫瘍(良性・悪性)などが原因で、これらの臓器が大きくなることがあります。
- 膀胱:膀胱は腎臓で作られた尿をためる臓器です。これが異常に大きくなるのは、排尿がうまくできていないサインで、尿路閉塞など命に関わる状態の可能性があります。特に雄猫に多く見られますが、雌にも起こることがあります。
- 消化管:胃や腸にガス・液体・異物・食べ物がたまると、お腹が膨らみます。特に注意が必要なのは、異物による腸閉塞が起きている場合です。
- 子宮:未避妊の雌猫では、妊娠による子宮の拡張のほか、液体や膿がたまる病的な拡張もあります。これはすぐに治療が必要です。また、避妊手術後に一時的に腹部が腫れることがあり、これは術後の過度な運動や縫合糸への反応が原因です。術後は安静にし、異変があれば早めに獣医師に相談しましょう。
- 消化管内寄生虫:コーネル猫医療センター*によると、寄生虫が腸にいると、猫のお腹が太鼓腹のように膨らむことがあります。特に子猫は成猫より影響を受けやすいです。寄生虫の有無は糞便検査で判明し、種類に応じた駆虫薬が処方されます。
- 腹部腫瘍:腹部の臓器に腫瘤ができると、お腹が膨らむことがあります。主に成猫に見られ、良性・悪性の両方があります。診断には検査が必要で、治療は手術、化学療法、投薬など状況に応じて行われます。

猫のお腹が膨らんでいるときの検査
猫のお腹が膨らんいる場合、状況に合わせて様々な検査が必要になります。血液検査、尿検査、腹部超音波検査・X線検査、胸部X線検査、貯留している内容物の評価、生検などが含まれます。場合によっては、より具体的な感染症の検査や臓器の詳しい検査が必要になることもあります。獣医師は、個々のペットの状態に応じて、必要な検査を選択し提案します。
猫のお腹が膨らんでいるときの治療
猫のお腹の膨らみを引き起こす原因に基づいて、適切な治療が選択されます。治療には外科的な処置や投薬治療が含まれますが、その優先順位やタイミングなどは、その原因疾患や病態レベル、および個々のケースの緊急性等によって異なります。難しい内容になることもあるかもしれませんが、できるだけペットの病態や治療について理解するように努め、わからないところは獣医師に尋ねましょう。飼い主としてできることは、普段からペットの様子をよく観察し、何らかの変化に気づいたときには動物病院を受診すること、そして病気の治療の際には指示された内容を遵守するようにすることです。疑問に思ったり、不安なことは自己判断せず、都度獣医師に相談するようにしましょう。


ジェシカ・セイドは、ニューイングランド地域で救急獣医師として活躍しています。ノースカロライナ州立獣医科大学を卒業し、10年以上この分野で活躍しています。診療をしていない時は、夫、娘、そしてフレンチブルドッグと過ごす時間を楽しんでいます。
関連記事

ウェットフードは一般的に猫が好み、味にうるさい猫にはぴったりな選択肢になります。ウェットフードの利点や与え方について確認しておきましょう。

猫の食性を理解して、理想的な食事回数を覚えておきましょう。また自動給餌器を利用する方法についても解説します。

トイレトレーニングをはじめ、様々なシチュエーションにあわせた愛猫のしつけにチャレンジする方も多いですよね。良い行いにはごほうびを与えるなど、トレーニングの目的にあわせた最適な方法をご紹介します。

胃腸の弱い猫について、深掘りしていきます。このようなケースでの食事の役割について学びましょう。

猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。






