
-
注目の製品
 アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス
アダルト 1~6歳 小粒 成犬用 ラム&ライス免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート
今すぐ購入 小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン
小型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも) 超小粒 高齢犬 7歳以上 チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン
中・大型犬用 マルチケア+シニア健康サポート(避妊・去勢後にも)中粒 高齢犬 7歳以上 (大型犬6歳以上) チキン【動物病院・専門店限定】独自の研究を重ねた果物や野菜、ビタミン等のブレンド「エイジングケアテクノロジー」が、脳の健康を維持し、毎日の活力をサポート
今すぐ購入 -
注目の記事
 ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類
ペットの大敵!犬や猫のノミ・ダニを駆除する薬の種類ノミやダニは不快なだけではなく、ペットの健康の大敵です。ノミ・ダニ駆除薬を投与されていない犬と猫は、ノミアレルギー性皮膚炎など、あらゆる病気のリスクがあります。どんな駆除薬の種類があるのかご紹介します。
続きを読む ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?
ペットがトカゲを食べてしまったら、どうすればいい?ペットがトカゲなどの生き物をイタズラしたり食べようとしたりすることはありませんか?こういった生き物については、少なくとも安全とは言えず、できるだけ接触させないようにする必要があります。その理由をご紹介します。
続きを読む 犬と猫の尿石症-尿中の結晶について
犬と猫の尿石症-尿中の結晶について犬と猫の尿石症、および尿中の結晶について解説します。尿中の結晶の種類や犬と猫の違いについて学びましょう。
続きを読む -

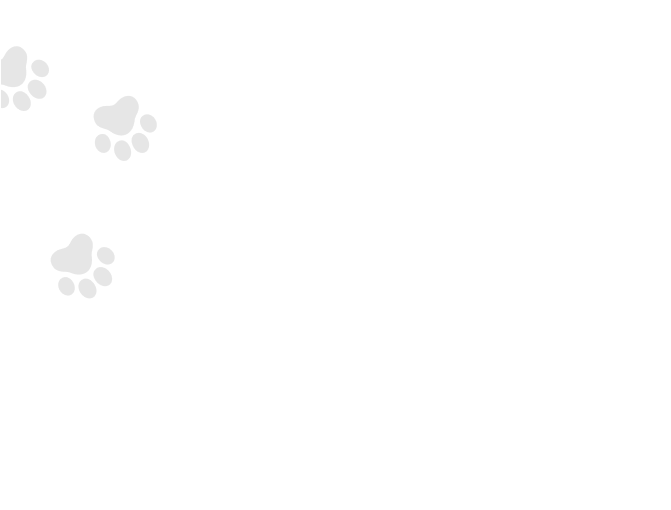
猫の去勢・避妊手術について
去勢・避妊とは、猫に妊娠をさせないために行う行為です。雄の場合を去勢、雌の場合を避妊といい、性成熟に達する頃に手術を行うことが一般的です。避妊・去勢を行うことで、望まない妊娠、繁殖を防ぐことができます。アメリカ動物虐待防止協会(ASPCA)によると、施設に保護される猫の頭数は年間で340万頭に上り、引き取り手となる家庭がまったく足りていない状況という、受け入れがたい事実もあります。
猫の去勢・避妊手術の流れ
猫の去勢・避妊手術は、動物病院にて全身麻酔下で行われます。そのため獣医師から術前および術後のケアについて説明と具体的な指示があります。手術前日の夜から食事と水を与えないようにし、予約時間に病院に連れて行きましょう。
雄猫の場合は、陰嚢を小さく切開し、中にある精巣を取り除きます。術創は吸収性の縫合糸または外科用接着剤で閉じます。手術後に合併症や問題が起こらない限り、手術当日の夜には帰宅することができます。雌猫の場合は、卵巣を取り出すため(子宮も一緒に切除することがあります)、大きな切開が必要になります。腹腔を開けるため、通常は、様子見のために一晩入院が必要ですが、翌日には退院できます。
猫の去勢・避妊手術の利点
前述の通り、去勢・避妊手術を行うことで、飼い主は望まない愛猫の妊娠、繁殖を防ぐことができます。一方で、猫自体にも病気の予防など健康面でのメリットがあります。
雌猫では、初回発情周期(繁殖できるようになること)が来る前に避妊を行うと、子宮頚がんになる確率が大きく低下します。また、卵巣を除去するため、卵巣がんが発生する確率はゼロになります。さらに、がん細胞の増殖を促進するホルモンの濃度が低下するため、乳がんになるリスクも減ります。
雄猫も同様に健康面での恩恵を受けることができます。去勢手術後は、性ホルモンが減少します。それによって、前立腺、精巣に関連する疾患リスク(前立腺肥大症、精巣がんなど)を低下させることができます。
また、交尾という猫の自然な行動によって伝播する病気もあります。VCA動物病院によると、猫白血病と猫エイズは咬傷を介して感染猫から他の猫に伝染する2種類の病気です(人のエイズや白血病とは異なり、猫から人に移ることはありません)。交尾や縄張り争いなど、猫同士がケンカする機会をなくすことで、これらの不治の病の感染を未然に防ぐことができます。
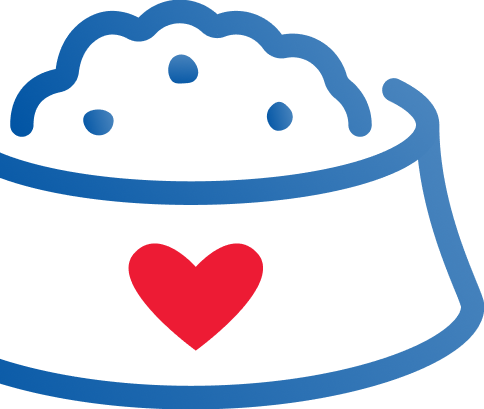

おいしいヒント
子猫は生後1年以内にワクチン接種のために複数回の通院が必要になる場合があります。成猫は一般的に年に1回の検診が効果的ですが、高齢猫や特別なケアが必要な猫はより頻繁な検診が必要になる場合があります。
猫の去勢・避妊手術後の性格や行動変化
猫の去勢・避妊には、飼い主、猫それぞれに利点があるとご理解いただけたと思います。次に、去勢・避妊手術後に起こる変化についても理解を深めましょう。去勢・避妊後の猫は、性格や行動に加え、太りやすくなるといった変化が見られることがあります。順を追って見ていきましょう。
去勢・避妊後に穏やかで、おとなしくなる
未去勢の雄猫は、ホルモンに突き動かされるまま交尾相手を探します。そのため侵入者からは、必要以上に縄張りを守ろうとします。その結果、同じ家に複数の未去勢雄が同居している場合は問題が発生しがちになります。特に発情中の雌猫が近くにいる場合、ケンカが起こりやすい傾向があります。去勢後は、このような雄猫の攻撃的な本能が抑制されることで穏やかで、おとなしい性格になることがあります。
攻撃的な側面が緩和されるのは、去勢後の雄猫だけでなく避妊後の雌猫にも見られます。避妊前の発情期には雄同様に攻撃的な行動を取ることがありますが、避妊後は、ホルモンバランスの安定によってストレスが軽減し、攻撃性が低下した穏やかな性格になることがあります。
去勢・避妊後に外出、徘徊が減る
発情中の雌猫は、ホルモンの作用と本能にしたがって交尾相手を探し求めます。もし単頭飼育だとしたら、あなたがドアを開けるたびに外に逃げ交尾相手を探そうとするでしょう。雄猫も同様です。ホルモンと交尾本能に支配されているため、同じようになんとか逃げようとします。避けなければならない最悪のケースは、屋外で事故に遭うことです。去勢・避妊後であれば、発情中の徘徊癖は抑えられ、事故に巻き込まれるリスクも低下します。
去勢・避妊後にマーキングが減る
雄猫は様々な目的でマーキングを行います。未去勢猫の場合、雄猫に対する縄張り主張、雌猫に対する性的アピールという役割を持ち、その臭いは特にきついです。去勢後は、性ホルモンが減少するので、マーキングしようとする雄猫の本能が抑えられ、臭いも弱くなります。
雌猫も発情期に分泌液を出します。この分泌物には、交尾の準備が整った雌が近くにいることを雄猫に知らせる香りが含まれています。避妊後の雌猫も雄同様に性ホルモンが減少しますので、このようなマーキング行動の抑制につながります。
去勢・避妊後に太りやすくなる
去勢・避妊手術後の猫は、太りやすくなることがあります。これには、性ホルモンの産生量の変化が影響しています。去勢・避妊後に性ホルモン量が変化することで、代謝の低下、食欲の増加、発情行動の抑制による運動量の減少など、猫の体重増加につながる要素が増えます。 したがって、不妊処置を終えた猫には、十分な運動量の維持、そして適切な食事が必要になります。ヒルズ サイエンス・ダイエット 避妊・去勢後~6歳 には、最適な体重を維持するために必要な栄養素とカロリーが適切なバランスで配合されています。
猫の去勢・避妊後のケアで気をつけること
去勢・避妊手術後は、体重管理以外にも気をつけておきたいことがあります。それは、不妊処置を終えた猫の回復ケアです。では、どのようなことに注意したらいいのか見ていきましょう。
安静にさせる
去勢・避妊に関わらず、手術後は必ず猫を安静にさせてあげてください。手術後は、肉体的にも精神的にもダメージを受けている状態です。したがって、猫が普段暮らす、慣れている環境で大人しく過ごせるようにしてあげましょう。
傷口の管理
特別な投薬や術後管理を必要とすることはほとんどありませんが、猫が傷口を引っ掻いたり、かじったり、舐めたりしないよう注意しましょう。エリザベスカラーという保護具を首の周りに着けるなどして対応してあげましょう。
食欲が戻るまで待つ
去勢・避妊手術を終えたばかりの頃は、食欲の低下が見られることがあります。また、全身麻酔によって消化器官が正常に働かないこともあります。この状態の猫に無理やり食事を与えると嘔吐してしまうこともあるので、食欲が戻るまで様子を見て、無理の無い範囲でご飯を与えるようにしましょう。
愛猫に去勢・避妊手術を受けさせることは不安かもしれませんが、望まない繁殖、将来の疾患リスクの低下などのメリットを考えると、それだけの価値があるでしょう。もし、去勢・避妊をまだ行なっていないのなら、かかりつけの獣医師に相談してみてください。


ジーン・グルナートは、バージニア州出身の作家、ブロガー、フリーランスライターです。バージニア州にある17エーカーの農場で、保護猫6匹と保護犬シャドウの世話をしています。
関連記事

胃腸の弱い猫について、深掘りしていきます。このようなケースでの食事の役割について学びましょう。

ウェットフードは一般的に猫が好み、味にうるさい猫にはぴったりな選択肢になります。ウェットフードの利点や与え方について確認しておきましょう。

猫の食性を理解して、理想的な食事回数を覚えておきましょう。また自動給餌器を利用する方法についても解説します。

トイレトレーニングをはじめ、様々なシチュエーションにあわせた愛猫のしつけにチャレンジする方も多いですよね。良い行いにはごほうびを与えるなど、トレーニングの目的にあわせた最適な方法をご紹介します。

猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。
猫に知られずにダイエットをさせる
低カロリーのフードで、猫の体重管理をサポートすることができます。無駄のない筋肉づくりに必要な高品質なたんぱく質を豊富に含み、風味豊かで栄養価の高い食事となるよう厳選された原材料を使用しています。臨床的に証明された抗酸化成分、ビタミンCとEが、健康な免疫システムの維持をサポートします。





